相続人が認知症の場合の注意点とは?認知症になる前の対策も解説
相続人が認知症になると、遺産分割協議や相続放棄などの意思表示が難しくなり、手続きが長期化するおそれがあります。成年後見制度を利用しても税優遇が受けられないなどの課題も生じるため、早めの対策が重要です。
本記事では、認知症相続人がいる場合の手続き上の注意点と、遺言・信託・任意後見など認知症発症前に取れる対策を具体的に紹介します。
相続人が認知症の場合の注意点
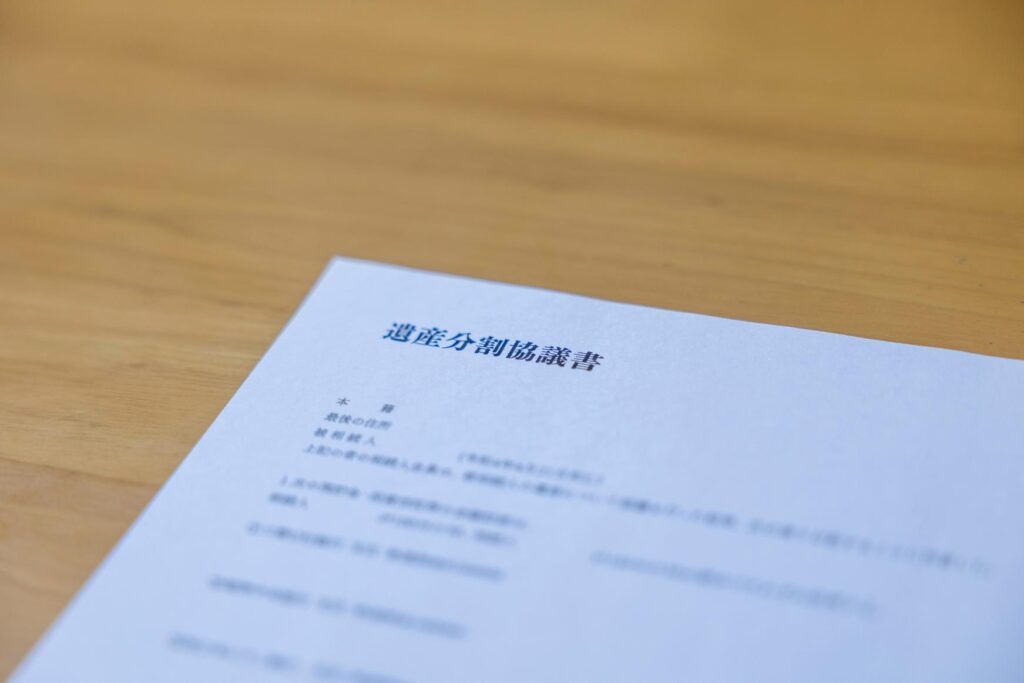
相続人が認知症になると、遺産分割協議ができなくなり、相続手続きが複雑化します。これから解説する注意点を理解し、適切な準備を進めることが重要です。
遺産分割協議はできない
相続人が認知症になった場合、遺産分割協議を行うことは原則としてできません。これは、遺産分割協議が各相続人の明確な意思表示に基づいて行われる必要があるためです。
認知症によって判断能力が著しく低下している場合、意思能力がないと見なされ、協議に参加する資格を失います。結果として、法定相続分に従った分割が適用されることになり、相続人間での合意が得られないまま、遺産が共有名義となるケースもあります。
共有名義の不動産や預貯金は管理や処分が難しく、トラブルの原因になるおそれがあります。このような状況を防ぐためには、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくなどの事前準備が不可欠です。成年後見制度の活用も有効な手段となります。
このような事態を避けるためには、認知症になる前に適切な対策を講じることが重要です。次のセクションでは、認知症の親が相続人となった場合の具体的な問題点について詳しく解説します。
認知症の相続人は相続放棄できない
認知症の相続人は、相続放棄の手続きを自ら行うことができません。相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述し、自らの意思で相続権を放棄する制度です。しかし、認知症によって判断能力が欠如している場合、法的に有効な意思表示と見なされないため、手続きが無効となります。
この結果、望まない負債を相続する可能性も否定できません。特に借金などマイナスの遺産がある場合には深刻です。認知症発症前に相続放棄の判断ができるよう、早めに専門家へ相談することが推奨されます。
なお、認知症の相続人が放棄手続きを進めるためには、成年後見制度を利用し、後見人を通じて申述する必要があります。
さらに、認知症の相続人がいる場合、他の相続人との間での遺産分割協議も複雑化します。認知症の相続人の意向を確認することができないため、遺産分割の合意形成が難しくなり、手続きが長引くことが予想されます。
認知症の人の代わりに何かを代筆する行為は無効になる
相続手続きにおいて、認知症の相続人がいる場合、その意思表示が難しくなるため、周囲の人が代わりに何かを代筆することを考えることがあります。しかし、法律上、認知症の人の代わりに行われた代筆行為は無効とされることが多いです。
これは、相続に関する重要な意思表示が本人の自由な意思に基づいて行われるべきであるという原則に基づいています。例えば、遺産分割協議や相続放棄の手続きにおいて、認知症の相続人が自らの意思で署名することができない場合、他の人がその代わりに署名を行うことは認められません。
このような行為は、相続人の権利を侵害する可能性があり、後々のトラブルの原因となることがあります。そのため、認知症の相続人がいる場合は、事前に適切な対策を講じることが重要です。
例えば、認知症になる前に遺言書を作成したり、成年後見制度を利用することで、相続手続きがスムーズに進むように準備をしておくことが推奨されます。これにより、認知症の相続人がいる場合でも、法的な問題を避けることができるでしょう。
認知症の親が相続人となったときの問題点

認知症の親が相続人となると、さまざまな問題が発生します。これから解説する問題を理解し、早めの対策を講じることが重要です。
税負担を下げる特例が使えない
相続人が認知症を患っている場合、その意思表示を代筆によって補おうとするのは法的に無効とされる可能性が高いです。遺産分割協議や相続放棄など、相続に関する重要な手続きは、本人の自由意思に基づく署名が求められるため、第三者が代筆した書類は無効となるおそれがあります。
例えば、遺産分割協議書に家族が代わりに署名した場合、それが本人の意思に基づくものであると証明できない限り、法的効力を持ちません。このような行為は後の争いの火種になる可能性があるため、認知症の兆候が見られる時点で、早めに対応することが重要です。
具体的には、公正証書遺言の作成や、成年後見制度の活用が推奨されます。特に後見人を選任することで、認知症の相続人の権利保護と円滑な相続手続きが可能になります。
また、特例を適用するためには、相続税の申告期限内に必要な手続きを完了させる必要がありますが、認知症の相続人がいることで手続きが長引くと、期限を過ぎてしまうリスクもあります。このような状況を避けるためには、認知症になる前にしっかりとした対策を講じておくことが重要です。
預金口座は相続手続きが完了するまで凍結される
相続人が認知症の場合、特に注意が必要なのが預金口座の扱いです。相続手続きが完了するまで、故人の預金口座は凍結されるため、相続人がその口座から資金を引き出すことができなくなります。
この凍結は、相続人が認知症であるかどうかに関わらず適用されるため、特に認知症の相続人がいる場合は、事前に対策を講じておくことが重要です。
預金口座が凍結されると、日常生活に必要な資金の管理が困難になることがあります。例えば、医療費や生活費の支払いが滞る可能性があるため、相続人が認知症である場合は、早めに相続手続きを進めることが求められます。
また、相続手続きには時間がかかることが多く、特に認知症の相続人がいる場合は、手続きがさらに複雑になることがあります。このような状況を避けるためには、遺言書の作成や成年後見制度の利用、民事信託の契約など、認知症になる前にできる対策を検討することが大切です。
不動産が共有名義になってしまう
相続人が認知症になると、遺産分割協議がスムーズに進まないことが多く、その結果として不動産が共有名義になってしまうリスクがあります。
共有名義になると、相続人全員の同意が必要となり、管理や売却、利用に関しても手続きが煩雑になります。特に、認知症の相続人がいる場合、その意思表示が難しくなるため、他の相続人との調整が一層困難になることが考えられます。
また、共有名義の不動産は、相続人の一人が売却を希望しても、他の相続人の同意がなければ実現できません。このため、相続人間でのトラブルが発生する可能性も高まります。さらに、共有名義の不動産は、相続税の評価額が高くなることもあり、税負担が増える要因ともなります。
このような事態を避けるためには、認知症になる前に適切な対策を講じることが重要です。遺言書の作成や、信託制度の利用など、事前に計画を立てておくことで、相続手続きが円滑に進むようにすることができます。
認知症で遺産分割協議ができないときに起こる問題とは

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議ができないため、さまざまな問題が発生します。これから解説する問題を未然に防ぐためには、早期の対策が求められます。
預貯金の払い戻しが制限されてしまう
相続人が認知症を患っている場合、預貯金の払い戻しに関して大きな制約が生じます。認知症の進行により、相続人が自らの意思で金融機関に対して手続きを行うことが難しくなるため、預金口座の管理が複雑化します。
具体的には、認知症の相続人がいる場合、金融機関はその人の意思能力を疑い、払い戻しを拒否することがあります。
このような状況では、相続手続きが完了するまで預金口座が凍結されることが一般的です。凍結された口座からは、相続人が必要とする資金を引き出すことができず、生活費や医療費の支払いに困るケースも少なくありません。
特に、認知症の相続人が高齢である場合、急な支出が発生することも考えられるため、事前に対策を講じておくことが重要です。
このような問題を避けるためには、認知症になる前に適切な手続きを行うことが求められます。例えば、遺言書の作成や成年後見制度の利用、民事信託の契約など、認知症発症前にできる対策を検討することが必要です。
法定相続分で決まった割合で相続するしかない
相続人が認知症を患っている場合、遺産分割協議が行えないため、相続の手続きは非常に複雑になります。特に、認知症の相続人がいる場合、遺産の分配は法定相続分に基づいて行われることになります。
法定相続分とは、民法に定められた相続人の権利に基づく割合であり、遺言書が存在しない場合にはこの割合に従って遺産が分配されます。このような状況では、相続人の意思を反映させることが難しく、相続財産の分配が不公平に感じられることもあります。
例えば、認知症の相続人が特定の財産を希望していたとしても、その意思を確認することができないため、法定相続分に従った分配が強制されることになります。このため、相続人間でのトラブルが発生する可能性も高まります。
また、法定相続分での相続は、相続税の負担にも影響を与えることがあります。相続税は相続財産の総額に基づいて計算されるため、認知症の相続人がいる場合、適切な対策を講じていないと、税負担が増加することも考えられます。
土地や家屋などの相続財産が共有となってしまう
相続人が認知症の場合、遺産分割協議が行えないため、土地や家屋などの不動産が共有名義となることが多くなります。これは、相続人全員が同意しない限り、個々の持分を明確にすることができないためです。
共有名義になると、各相続人はその不動産に対して持分を持つことになりますが、これが後々のトラブルの原因となることがあります。
例えば、共有名義の不動産を売却したい場合、全ての相続人の同意が必要です。認知症の相続人がいる場合、その意思表示が難しくなるため、売却手続きが進まないことが考えられます。
また、共有名義の不動産は、管理や維持に関する責任も共有されるため、相続人間での意見の相違が生じると、管理が行き届かなくなる可能性もあります。
さらに、共有名義の不動産は、相続人の一人が亡くなった場合、その持分が新たな相続の対象となり、さらに複雑な相続問題を引き起こすことがあります。このような事態を避けるためにも、認知症になる前に適切な対策を講じることが重要です。
相続人が認知症になる前にできることとは
相続人が認知症になる前に、適切な対策を講じることが重要です。これから解説する対策法を行うことで、相続人が認知症になった後に後悔しないようにしていくことが重要です。
遺言書(公正証書遺言)を作成する
認知症のリスクがある相続人がいる場合、遺言書の作成は非常に重要な対策となります。特に公正証書遺言は、法律的な効力が強く、相続人の意思を明確に示す手段として有効です。
公正証書遺言は、公証人が立ち会いのもとで作成されるため、形式的な要件が満たされており、後々のトラブルを避けることができます。
遺言書を作成することで、相続人が認知症になった場合でも、遺産分割についての意思が明確に示されるため、遺産分割協議がスムーズに進む可能性が高まります。
また、遺言書には特定の相続人に特定の財産を相続させる旨を記載することができるため、相続人間の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。さらに、公正証書遺言は、作成後に公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低くなります。
認知症の進行を考慮し、早めに遺言書を作成することが、相続手続きの円滑化につながるのです。相続人が認知症になる前に、しっかりとした対策を講じることが、将来のトラブルを避けるための第一歩となります。
成年後見制度(任意後見制度)を利用する
成年後見制度は、認知症などの理由で判断能力が不十分な方の権利を保護するための制度です。この制度を利用することで、相続人が認知症になった場合でも、適切な手続きを進めることが可能になります。
特に、任意後見制度は、本人が元気なうちに後見人を選任し、将来の判断能力が低下した際に備えることができるため、非常に有効な手段です。
任意後見制度を利用するためには、まず本人が後見人を選び、その選任を公正証書で行う必要があります。この公正証書は、法的な効力を持ち、後見人が本人の財産管理や生活支援を行う際の根拠となります。後見人には、信頼できる家族や友人を選ぶことが重要で、本人の意向を尊重した支援が求められます。
また、成年後見制度を利用することで、相続手続きにおいてもスムーズに進めることができます。認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議や相続放棄などの意思表示が難しくなるため、後見人が代理で手続きを行うことができるのです。
ただし、成年後見制度には税優遇が受けられないというデメリットも存在します。そのため、制度を利用する際には、事前に十分な情報収集と検討が必要です。
民事信託(家族信託)を契約する
民事信託、特に家族信託は、認知症のリスクを考慮した相続対策として非常に有効な手段です。家族信託を利用することで、相続人が認知症になった場合でも、財産の管理や分配をスムーズに行うことが可能になります。
信託契約を結ぶことで、信託財産の管理者(受託者)を指定し、認知症の相続人が意思表示できない状況でも、受託者が適切に財産を管理し、分配することができます。
家族信託の最大の利点は、相続人が認知症になった場合でも、事前に設定した条件に基づいて財産を管理できる点です。これにより、遺産分割協議ができない状況でも、信託契約に従って財産の分配が行われるため、手続きが長期化するリスクを軽減できます。
さらに、家族信託を利用することで、相続税の負担を軽減することも期待できます。信託財産は、受託者が管理するため、相続人が直接管理する場合と比べて、税務上の優遇措置を受けられる可能性があります。
ただし、信託契約を結ぶ際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。信託の内容や条件を適切に設定することで、将来的なトラブルを避けることができます。
生前贈与を行う
生前贈与は、相続人が認知症になる前に行うことができる有効な対策の一つです。生前贈与を通じて、財産を早めに受け渡すことで、相続手続きの複雑さを軽減し、認知症による意思能力の低下を避けることができます。
特に、親から子への贈与は一般的であり、贈与税の非課税枠を利用することで、税負担を軽減することも可能です。生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にすることが重要です。
また、贈与を受けた財産については、贈与税が課税される場合がありますので、事前に税務署や専門家に相談することをお勧めします。特に、贈与税の基礎控除額を超える場合には、適切な手続きを行う必要があります。
さらに、生前贈与は相続財産の減少を図るだけでなく、相続人間のトラブルを未然に防ぐ効果もあります。贈与を通じて、相続人がどのように財産を受け取るかを明確にすることで、将来的な争いを避けることができるのです。
まとめ
相続人が認知症になると、遺産分割協議や相続放棄などの手続きが複雑化し、長期化する可能性があります。認知症の相続人がいる場合、法的な意思表示が難しくなるため、早めの対策が求められます。
特に、遺産分割協議ができないことや相続放棄ができないこと、代筆行為が無効になることなど、注意すべき点が多く存在します。
また、認知症の親が相続人となった場合には、税負担を下げる特例が使えないことや、預金口座が凍結されること、不動産が共有名義になってしまうリスクも考慮しなければなりません。これらの問題は、相続手続きにおいて大きな障害となるため、事前に対策を講じることが重要です。
認知症になる前に、遺言書の作成や成年後見制度の利用、民事信託の契約、生前贈与などの手段を検討することで、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。これらの対策を通じて、家族の負担を軽減し、円滑な相続を実現することができるでしょう。



