相続人に障害者がいる場合に起きることとは?障害者控除の要件も解説
相続人に障害者がいる場合、成年後見人の選任や障害者控除など特有の手続きが必要になります。適切な制度を活用しないと、相続税負担や遺産管理に関するトラブルが発生しかねません。
本記事では、障害者控除の適用条件と計算方法、家族信託や公正証書遺言などの準備策を整理し、安心して財産継承を行うためのポイントを解説します。
相続人に障害者がいる場合に起きることとは
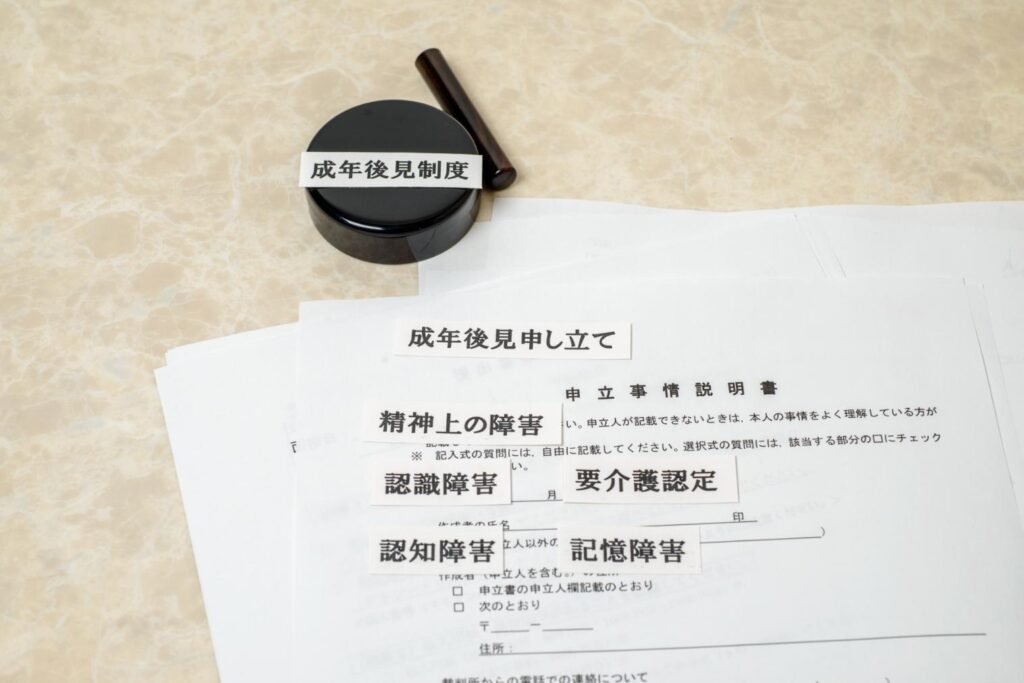
相続人に障害者がいる場合に起きることとは、相続手続きにおいて特有の課題が生じることを意味します。これから解説することを理解し、相続税負担や遺産管理に関するトラブルを避けるための適切な手続きが求められます。
成年後見人なしで手続きが可能になる
相続人に障害者がいる場合でも、本人に十分な判断能力があり、かつ他の相続人全員が内容に同意すれば、成年後見人を付けずに遺産分割協議を進められるケースがあります。
具体的には、医師の診断書などで意思能力が確認され、公証人立会いのもとで遺産分割協議書へ署名・押印すれば、法的に有効と認められる可能性が高いです。
ただし、判断能力が低下しているか判断が微妙な場合には、協議後に無効を主張されるリスクが残り、預貯金の払戻しや不動産登記が止まる事態も想定されます。
また、相続税申告時に障害者控除を適用するには障害者手帳等の証明が必要となるため、医療証明と一緒に準備しておくと手続きが円滑です。さらに、相続財産に未上場株式や収益不動産が含まれる場合には、評価額の妥当性や将来の管理負担を巡って合意形成が難航する傾向があります。
こうした複雑な資産を含むときほど、専門家が第三者として立会い、議事録を残しておくと、後に意思能力を問題視されても手続きの適正を証明しやすくなります。このとき、金融機関では本人確認手続きが厳格化されているため、顔写真付き身分証の用意も忘れないでください。
成年後見人を選任して遺産分割できる
相続人に障害者がいる場合、判断能力に制限があるときは家庭裁判所へ成年後見開始を申し立て、選任された成年後見人が遺産分割協議に参加する方法が原則です。
成年後見人は相続財産の管理・分割について代理権を持つため、障害者本人が意思表明できない状況でも、協議の有効性と障害者の権利保護を同時に担保できます。
申立てには戸籍謄本、診断書、財産目録などを添え、通常は審理期間として1〜2か月程度を見込む必要があります。選任後は、後見監督人の指導下で財産管理計画を作成し、相続税の障害者控除を適用しつつ分割案を検討するのが一般的な流れです。
なお、成年後見人自身が他の相続人である場合は利益相反が生じるため、別の第三者後見人を選ぶか、特別代理人選任を申し立てる必要があります。
特に、高額不動産や自社株を含む分割では、換価処分と現物分与のどちらが本人利益に適うかを後見人が精査し、裁判所の許可を経て実行する義務があります。
法定相続分で相続を行う
相続人に障害者がいる場合でも民法の法定相続分は変わらず、配偶者と子が相続人なら配偶者2分の1・子全体で2分の1など通常の割合が適用されます。
したがって、遺言書がない場合はまず法定相続分を基準に協議書を作成し、障害者には相応分の財産を確保することが前提となります。もっとも、障害者の生活費が長期にわたって必要となる場合には、民法907条2項の特別受益・寄与分や遺留分制度を活用し、分配方法を柔軟に調整することが望ましいです。
さらに、相続税の障害者控除を適用すれば納税額を圧縮できるため、現金分配を増やし控除額を最大化する設計が有効です。不動産を障害者が共有持分で取得すると将来の売却や賃貸が困難になるため、代償分割や換価分割で現金化しておくと管理負担を軽減できます。
分割方法が確定したら、登記事項証明書や相続税申告書に障害者控除欄を記載し、控除計算を添付することで手続きは完了します。
加えて、家族信託や後見制度支援信託を組み合わせれば、定期的に生活費を給付しつつ財産の散逸を防げるため、将来の介護費や医療費に備えた長期的な資金管理策として有効です。
相続税の障害者控除の要件

相続税の障害者控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。これから説明する条件を確認することで、適切な控除を受けることが可能になります。
85歳未満の障害者であること
相続税の障害者控除を受けるための要件の一つに、相続人が85歳未満の障害者であることが挙げられます。この要件は、障害者控除の適用を受けるために非常に重要です。
具体的には、障害者と認定されるためには、身体的または精神的な障害があることが必要であり、その障害の程度によって控除額が異なる場合があります。
85歳未満という年齢制限は、相続税法において特に設けられており、これに該当する障害者が相続人である場合、相続税の負担を軽減することが可能です。障害者控除を適用することで、相続税の計算において一定の金額が控除されるため、相続人にとっては大きなメリットとなります。
この要件を満たすためには、障害者手帳の取得や医師の診断書が必要になることが多く、事前に準備をしておくことが重要です。また、相続手続きにおいては、障害者控除の適用を受けるための書類を正確に整えることが求められます。
日本国内に住所があること
相続税の障害者控除を受けるためには、相続人が日本国内に住所を有していることが重要な要件となります。具体的には、相続人が日本に住民登録をしていることが求められます。
この要件は、相続税の適用を受けるための基本的な条件であり、国内に居住していることが確認できなければ、控除の対象外となる可能性があります。
住所の確認は、住民票やその他の公的書類を通じて行われます。相続人が日本国内に居住していることを証明するためには、これらの書類を用意し、相続手続きの際に提出する必要があります。
また、相続人が海外に居住している場合でも、日本国内に住所を持つ親族がいる場合には、その親族が相続手続きを行うことが可能です。しかし、この場合でも、障害者控除を受けるためには、相続人自身が日本国内に住所を有している必要があります。
したがって、相続人の居住状況を正確に把握し、必要な手続きを適切に進めることが、相続税負担を軽減するための重要なステップとなります。
法定相続人であること
相続において、障害者が法定相続人であることは非常に重要なポイントです。法定相続人とは、民法に定められた相続権を持つ者のことで、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが該当します。
まず、障害者が相続人である場合、相続手続きにおいて成年後見人の選任が求められることがあります。成年後見人は、障害者の財産管理や法律行為をサポートする役割を果たします。これにより、障害者が適切に相続財産を受け取ることができるようになります。
また、法定相続分に基づいて相続が行われるため、障害者が受け取る相続財産の割合は他の相続人と同じです。ただし、障害者控除などの特例を利用することで、相続税の負担を軽減することも可能です。これにより、障害者が受け取る財産がより多く残ることが期待できます。
このように、障害者が法定相続人である場合には、相続手続きにおいて特別な配慮が必要ですが、適切な手続きを踏むことで、安心して財産を継承することができます。
相続財産を取得すること
相続人に障害者がいる場合、相続財産を取得することは重要なステップです。障害者が法定相続人である場合、相続財産の取得に関して特別な配慮が必要となります。
まず、障害者が相続財産を取得する際には、相続税の障害者控除が適用される可能性があります。この控除を利用することで、相続税の負担を軽減することができるため、財産を受け取る際の経済的な負担を軽減することが期待できます。
また、障害者が相続財産を取得する場合、成年後見人が選任されているかどうかも重要なポイントです。成年後見人がいる場合、相続手続きは後見人を通じて行われるため、障害者本人が直接手続きを行う必要がなくなります。
さらに、相続財産の取得に際しては、遺産分割協議が必要となりますが、障害者がいる場合には特に配慮が求められます。相続人全員が合意することが重要であり、障害者の権利を尊重した分割方法を検討することが求められます。
相続人が障害者の時に準備しておきたい契約とは
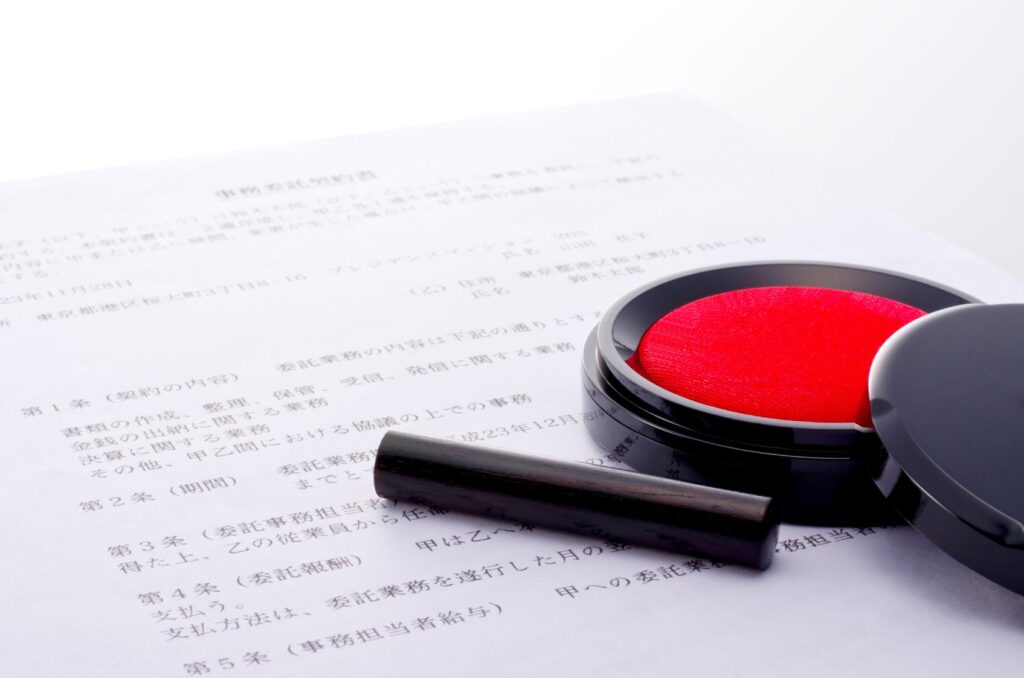
相続人に障害者がいる場合、適切な契約を準備することが重要です。これから解説する内容を踏まえて、相続人が障害者の時にいくつかの契約を検討しておきましょう。
公正証書遺言
相続人が障害者であるとき、公正証書遺言は遺産配分を明確にし紛争を防ぐ最重要ツールです。公証役場で作成するため偽造の懸念が少なく、公証人と証人二人の立会いにより遺言能力も確実に確認されます。
障害者には生活費確保のため現金や信託受益権を重点配分し、管理方法として成年後見人や受託者を指定する条項を盛り込みます。
署名が困難な場合でも口授方式が利用でき、精神障害の場合は医師の診断書で意思能力を補強できます。遺言書は公証役場で20年間保管され、閲覧制度により相続人が容易に内容を確認できるため、遺言不存在を巡る訴訟リスクを大幅に削減します。
手数料は財産1億円以下で2万円台から、証人謝礼は1人5千円程度が目安です。遺留分配慮条項や預金払戻し代理権も併記し、生命保険金の受取人を障害者信託へ変更するなど周辺契約と一体で設計すると効果が最大化します。
さらに、公正証書遺言は、遺言者が生前に公証人と相談しながら作成することができるため、法律的な知識が不十分な場合でも安心して手続きを進めることができます。
家族信託契約
相続人が障害者の場合、家族信託契約を組成すれば親亡き後も受託者が資産を運用し、障害者受益者へ定期給付する仕組みを確立できます。
また、委託者が不動産や金融資産を信託し、受益権を障害者に帰属させれば、成年後見制度の使途制限を回避しつつ柔軟な資金管理が可能です。契約書には医療費・介護費を目的外支出として認める条項や予備受託者指定を盛り込み、30年超の長期運用に備えます。
さらに、信託財産は委託者死亡時に相続税課税されますが、障害者控除を活用すれば納税額を抑制できます。受託者は信託口座を開設し毎年収支報告を行う義務があり透明性が保たれます。不動産は受託者名義に登記し第三者対抗要件を確保します。
信託報酬は年間0.5〜1%が上限の例が多く、家族型の方がコスト効率が高い傾向です。任意後見・死後事務委任と組み合わせると、生活支援から相続実務まで一貫して管理でき安心です。
任意後見契約
相続人が障害者で将来の判断能力低下が懸念されるとき、任意後見契約を結べば本人が元気なうちに信頼できる支援者を指名できます。公証役場で公正証書を作成し登記すると効力が確保され、必要時に家庭裁判所が任意後見監督人を選任して契約が発効します。
任意後見人は財産管理や医療契約の代理を担い、成年後見より柔軟で利益相反の少ない支援が可能です。相続税の障害者控除を踏まえた納税や信託口座への資金振替も行え、死後事務委任と連携すれば死亡後の事務も一体的に対応できます。
費用は契約時手数料約1万円、発効後は監督人報酬として月1〜2万円が目安です。精神障害や知的障害でも診断書で意思能力を証明すれば契約可能で、内容を定期的に見直すことが重要です。
このように、任意後見契約は相続人に障害者がいる場合において、安心して財産管理や生活支援を受けるための有効な手段となります。事前にしっかりと準備を行うことで、将来の不安を軽減し、スムーズな相続手続きを実現することができるでしょう。
財産管理等委任契約
相続人が障害者で日常の財産管理が難しい場合、財産管理等委任契約を結ぶことで信頼できる家族や専門職が預金管理や納税、公共料金支払いを代行できます。任意後見発効前から利用でき、銀行取引や不動産更新など即時性が求められる手続きにも対応します。
契約は公正証書で作成し、委任事項・報酬・監査方法を詳細に定めて浪費や横領リスクを低減します。受任者が家族でも年間5〜10万円の管理報酬を設定し、収支報告を共有すれば相続開始後の財産目録作成が容易です。
障害者控除見込み額を試算し保険や信託への資金移動を委任事項に加えると相続税対策が広がります。公証人手数料は1通約1万円、司法書士依頼時は+ 3〜5万円が相場で、管理報酬は確定申告時に必要経費に計上できる場合があります。
自治体の後見支援センターに届出を行えば第三者の定期チェックも受けられ、任意後見への移行をスムーズに行えます。このように、財産管理等委任契約は、相続人に障害者がいる場合において、財産の適切な管理を実現するための有効な手段となります。
死後事務委任契約
相続人が障害者の場合、被相続人が死後事務委任契約を締結しておくと、葬儀・埋葬手配や年金・保険解約、公共サービス名義変更を第三者に包括委任できます。
契約は公正証書で作成し、委任事項と報酬、資金源を明記することで障害者の負担を大幅に軽減します。死後事務は財産分配ではなく事務処理に限定されるため、遺言や家族信託と併用して承継を指示することが不可欠です。
報酬は専門職へ依頼する場合20万〜50万円が相場ですが、親族なら無償設定も可能です。葬儀の宗派や遺品整理業者の指定、障害者への形見分け方法を細かく規定すれば遺族間の解釈相違を防げます。
また、死後事務委任契約は、相続人の意向を反映させることができるため、遺族間のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
契約内容には、具体的な手続きの指示や希望する葬儀のスタイル、遺品の取り扱いに関する詳細を盛り込むことができるため、事前にしっかりと話し合いを行うことが重要です。
見守り契約
相続人が障害者で遠方に住む家族が日常支援できない場合、見守り契約を結べば専門家やNPOが定期訪問や電話連絡を行い健康状態や生活環境を確認します。契約は公正証書で作成し、頻度・方法・報告先を明文化するため安否確認より信頼性が高まります。
異変時には、医師診察や緊急搬送、任意後見申立てを行う権限を付与でき安全網として機能します。費用は月1回訪問で5千〜1万円が目安で、地域包括支援センターと連携すれば助成制度を利用できる場合もあります。
契約は地域見守りネットワークと連動させ災害時の避難支援対象者名簿登録にも役立ちます。緊急通報装置や日用品購入代行をセットにすると障害者のQOLが向上し、記録の共有も非常に簡単です
見守り契約を通じて、障害者の権利を守りつつ、家族や支援者が協力して生活を支える体制を築くことができます。相続に関する手続きや財産管理を円滑に進めるためにも、見守り契約の活用を検討することが大切です。
まとめ
相続人に障害者がいる場合、特有の手続きや配慮が必要であることがわかりました。成年後見人の選任や障害者控除の適用など、適切な制度を利用することで、相続税の負担を軽減し、遺産管理に関するトラブルを避けることが可能です。
また、相続人が障害者である場合には、公正証書遺言や家族信託契約、任意後見契約など、さまざまな契約を準備することで、将来的な不安を軽減することができます。これらの契約は、障害者が安心して財産を受け継ぐための重要な手段となります。
相続は一度きりの大切なプロセスですので、専門家のアドバイスを受けながら、しっかりと準備を進めることが求められます。障害者がいる場合でも、適切な対策を講じることで、スムーズな相続を実現し、家族の絆を守ることができるでしょう。



