相続放棄の時の国庫帰属の手続きとは?相続土地国庫帰属制度のメリットも解説
使い道のない山林や空き地を相続するかもしれないと不安な方に向けて、相続放棄と国庫帰属の手続きを整理します。相続土地国庫帰属制度を利用すれば、負担金を納めるだけで土地を国に引き取ってもらえますが、審査は厳格です。
本記事では、申請の流れ、書類作成のポイント、却下されやすい土地の特徴、承認後の費用負担、代替策まで丁寧に解説します。検討材料としてお読みください。
相続放棄の時に国庫帰属の手続きとは

相続放棄を選択した場合、国庫帰属の手続きが必要です。この手続きは、使い道のない土地を国に引き取ってもらうためのもので、まずは法務局への相談から始まります。
法務局への相談を行う
相続放棄を検討する際、まず重要なのは法務局への相談です。相続に関する手続きは複雑であり、特に国庫帰属制度を利用する場合は、専門的な知識が求められます。
法務局では、相続放棄の手続きや国庫帰属に関する具体的な情報を提供してくれるため、まずは相談を行うことが推奨されます。
相談の際には、相続する土地の状況や、相続人の人数、相続放棄を希望する理由などを詳しく説明することが大切です。これにより、法務局の職員は適切なアドバイスを行いやすくなります。
また、必要な書類や手続きの流れについても教えてもらえるため、事前に準備を進めることが可能です。
さらに、法務局では相続放棄に関する書類の提出先や期限についても案内してくれます。特に、相続放棄には期限があるため、早めに相談し、必要な手続きを把握しておくことが重要です。
申請書類の作成・提出する
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、申請書類の作成と提出が不可欠です。まず、必要な書類を揃えることから始めましょう。
主な書類には、相続関係を証明する戸籍謄本や、土地の登記簿謄本、申請書自体が含まれます。これらの書類は、相続人の権利を明確にし、国庫帰属の手続きをスムーズに進めるために重要です。
書類を作成する際は、正確性が求められます。特に、土地の情報や相続人の情報に誤りがあると、申請が却下される可能性が高まります。したがって、記入内容を何度も確認し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
書類が揃ったら、法務局に提出します。提出方法は、直接持参するか郵送することができますが、直接持参する場合は、事前に予約をしておくとスムーズです。
提出後は、審査が行われ、承認されるまでの期間は数週間から数ヶ月かかることがありますので、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
承認後の負担金を納付する
相続土地国庫帰属制度において、国に土地を引き取ってもらうためには、申請が承認された後に負担金を納付する必要があります。
この負担金は、土地の面積や評価額に基づいて算出されるため、事前にどの程度の金額が必要になるのかを把握しておくことが重要です。
負担金の納付は、承認通知を受け取った後、指定された期限内に行わなければなりません。期限を過ぎてしまうと、承認が取り消される可能性があるため、注意が必要です。
また、納付方法については、銀行振込や窓口での支払いなど、複数の選択肢が用意されていますが、事前に確認しておくことをお勧めします。
さらに、負担金を納付した後は、国からの正式な受領証が発行されます。この受領証は、土地が国に帰属したことを証明する重要な書類となるため、大切に保管しておくことが求められます。これにより、今後のトラブルを避けることができるでしょう。
相続土地国庫帰属制度のメリットとは
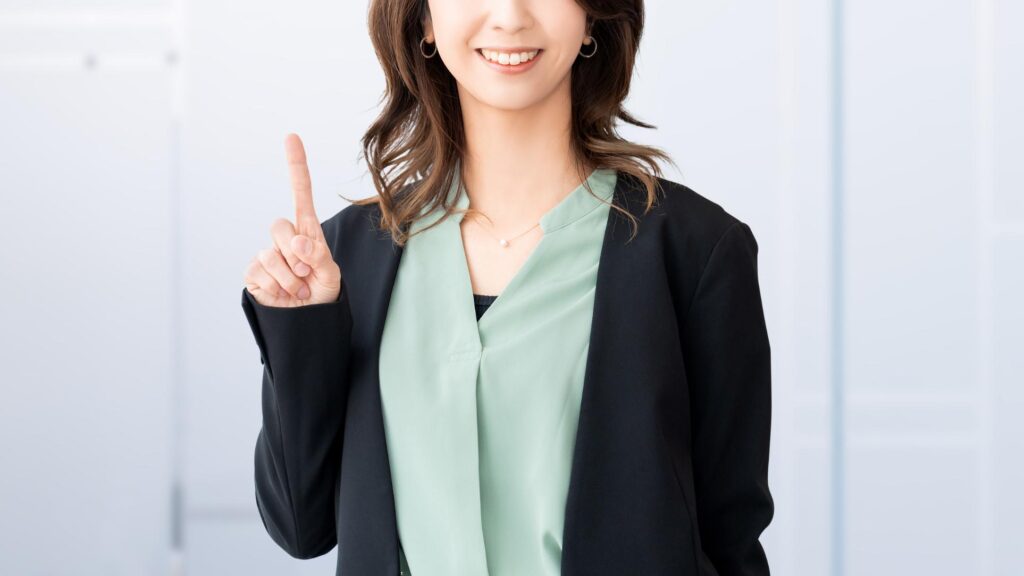
相続土地国庫帰属制度には、いくつかのメリットがあります。これから説明するメリットを踏まえると、相続土地国庫帰属制度の利用をお勧めします。
売却できない土地を手放すことができる
相続土地国庫帰属制度の大きなメリットの一つは、売却が難しい土地を手放すことができる点です。
特に、山林や空き地などの利用価値が低い土地は、相続したものの維持管理にかかる費用や手間が負担となることがあります。この制度を利用することで、そうした土地を国に引き取ってもらうことが可能になります。
土地の売却が難しい理由はさまざまですが、例えば、立地条件が悪い、周囲にインフラが整っていない、または土地の形状が不整形であるなどが挙げられます。
こうした土地は、一般的な不動産市場では需要が少なく、売却が困難です。そのため、相続した土地が負担となり、相続放棄を考える方も多いのが現状です。
国庫帰属制度を利用することで、相続放棄をすることなく、土地を手放す選択肢が増えます。手続きは必要ですが、負担金を納めることで、国が土地を引き取ってくれるため、長期的な管理や維持費用を心配する必要がなくなります。
土地の引き取り手を自分で探す必要がない
相続土地国庫帰属制度の大きなメリットの一つは、土地の引き取り手を自分で探す必要がない点です。通常、相続した土地が不要な場合、売却や寄付、または他の方法で手放すことを考える必要がありますが、これには時間や労力がかかります。
特に、山林や空き地などの利用価値が低い土地の場合、買い手を見つけるのは容易ではありません。しかし、国庫帰属制度を利用すれば、土地を国に引き取ってもらうことができるため、面倒な手続きを省略できます。
申請が承認されれば、土地は国の管理下に置かれ、相続人はその土地に関する責任から解放されます。これにより、相続人は不必要な負担を軽減し、他の重要な事柄に集中することが可能になります。
また、国が土地を管理するため、相続人が土地の維持管理や税金の支払いを行う必要もなくなります。これにより、特に遠方に住んでいる相続人にとっては、物理的な管理の手間が省けるという大きな利点があります。
管理を国が行っているので安心感がある
相続土地国庫帰属制度の大きなメリットの一つは、土地の管理を国が行ってくれる点です。
相続した土地が使い道のない山林や空き地であった場合、維持管理にかかる費用や手間が大きな負担となることがあります。しかし、この制度を利用することで、そうした負担から解放されるのです。
国が土地を引き取ることで、土地の管理や維持に関する責任が国に移ります。これにより、相続人は土地の管理に関する心配をせずに済むため、精神的な安心感を得ることができます。
また、国が管理することで、土地の適切な利用や保全が期待できるため、地域社会にとってもプラスの影響を与えることができます。
さらに、国による管理は、土地の価値を維持するための施策が講じられることを意味します。例えば、環境保護や地域振興の観点から、国が適切な管理を行うことで、将来的に土地の価値が上がる可能性もあります。
国庫帰属が認められない土地の種類とは

相続土地国庫帰属制度には、国庫帰属が認められない土地の種類があります。これから解説する認められない条件を理解しておくことが重要です。
建物がある土地
相続土地国庫帰属制度では、土地の引き取りを国に依頼することができますが、建物がある土地については特に注意が必要です。基本的に、建物が存在する土地は国庫帰属の対象外となります。
これは、建物があることで土地の利用価値が変わり、単純に国に引き渡すことができないためです。例えば、相続した土地に古い家屋が建っている場合、その土地は国に帰属させることができません。
このような土地は、相続人が自ら管理するか、売却を検討する必要があります。売却が難しい場合には、解体して更地にする選択肢も考えられますが、解体費用がかかるため、経済的な負担が増えることもあります。
また、建物がある土地を相続する際には、相続放棄を選択することも可能ですが、放棄の手続きには期限があり、慎重な判断が求められます。
相続放棄を行うことで、相続人は土地や建物に関する権利や義務を放棄することができますが、一度放棄すると撤回はできないため、十分な検討が必要です。
担保権などが設定されている土地
相続土地国庫帰属制度を利用する際、担保権が設定されている土地は国庫帰属の対象外となります。担保権とは、土地や建物を担保にして借入を行った際に設定される権利であり、債権者がその土地を優先的に処分できる権利を持つことを意味します。
このため、担保権が設定された土地は、相続放棄を行ったとしても、国に引き取ってもらうことができません。
担保権が設定されている土地を相続した場合、まずはその担保権の内容を確認することが重要です。担保権が残っている限り、土地の所有権を放棄しても、債権者がその土地に対して権利を主張することができます。
また、担保権が設定されている土地は、相続放棄の手続きが複雑になることがあります。特に、担保権の設定が解除されない限り、国庫帰属の申請ができないため、早めに専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄を行う際には、土地の状況をしっかりと把握し、適切な手続きを進めることが重要です。
通路などが含まれる土地
相続土地国庫帰属制度において、国庫帰属が認められない土地の一つに「通路などが含まれる土地」があります。
通路が含まれる土地は、他の土地との関係性が強いため、国庫帰属の審査においても厳格に判断されます。例えば、通路が他の土地の利用に不可欠である場合、その土地を国に引き取ってもらうことはできません。
これは、通路が他の土地の所有者にとって重要なアクセス手段であるため、国がその土地を引き取ることによって生じる問題を避けるためです。
また、通路が含まれる土地は、相続人にとっても管理や利用において複雑な問題を引き起こす可能性があります。
通路の利用権を持つ他の土地の所有者との関係を考慮しなければならず、場合によってはトラブルの原因となることもあります。このため、相続放棄を検討する際には、通路が含まれる土地の特性を十分に理解し、慎重に判断することが重要です。
所有権について争いがある土地
相続土地国庫帰属制度を利用する際、所有権について争いがある土地は、申請が認められない重要な要素の一つです。
具体的には、相続人同士で土地の権利を巡る争いが生じている場合、その土地は国に引き取ってもらうことができません。これは、国が所有権の明確性を重視しているためであり、争いが解決されない限り、土地の処理ができないからです。
このような土地を相続する場合、まずは相続人間での話し合いを行い、所有権の確定を目指すことが重要です。
話し合いが難航する場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは法律的な観点から適切なアドバイスを提供し、争いを解決する手助けをしてくれるでしょう。
また、所有権の争いが解決した後でも、国庫帰属の手続きには一定の条件があるため、事前に必要な書類や手続きについて確認しておくことが大切です。これにより、スムーズに手続きを進めることができ、無駄な時間や労力を省くことができます。
土地を相続放棄する時の注意点とは

土地を相続放棄する際には、いくつかの重要な注意点があります。これから解説する注意点を踏まえて、正しく相続放棄を行いましょう。
土地と建物の登記名義が異なる場合は手続きが増える
土地のみ被相続人名義、建物は配偶者や第三者名義というケースで相続放棄をすると、家庭裁判所の申述は一度で済むものの、その後の名義整理は自動では進みません。
土地は宙に浮いた状態となり、固定資産税の納税通知だけが被相続人宛てに届き続け、実際の管理責任は次順位相続人へ次々に移転します。
放棄人がいなくても行政は「所有者不明土地」として課税し続け、草刈りや倒壊危険が放置されれば空家特措法に基づく行政代執行で解体費用を請求される例もあります。
こうした二重名義を放置しないためには、登記事項証明で所有者を確定したうえで、管理協定・共有物分割・信託設定など早期に出口策を決めることが不可欠です。
司法書士や土地家屋調査士に依頼し、建物所有者と連携して売却や取壊しの同意をとり付けることで、後の費用負担と手間を大幅に減らせます。
期限を過ぎると相続放棄できない
相続放棄の熟慮期間は民法915条で「相続の開始を知った日から3か月」と定められ、この期限を1日でも超えると単純承認と扱われ山林や農地、瑕疵物件も含めて自動的に承継します。
また、換金が難しい土地は管理費と固定資産税が恒久的に発生し、自治体の雑草除去命令に応じなければ過料を科される恐れもあります。
財産全容が掴めない場合は、期間内に家庭裁判所へ「熟慮期間伸長」の申立てを行えば数か月の猶予が得られますが、残高証明や評価証明など客観資料を添え「調査中である理由」を示す必要があります。
申述書は到達日基準で審査されるため、締切直前は配達証明付き速達を使い、追跡番号と到着日をスクリーンショットで残しておくと安全です。連休や年末年始を挟む場合は窓口休庁日に注意し、事前に管轄家庭裁判所へ郵券額や必要部数を確認しておきましょう。
このため、相続放棄を考えている場合は、早めに専門家に相談し、必要な手続きを確認することをお勧めします。
相続放棄すると撤回や取消しはできない
相続放棄を選択する際には、その決定が最終的なものであることを理解しておく必要があります。
相続放棄を行うと、相続人はその相続財産に対する一切の権利を放棄することになります。このため、一度放棄を行った後に「やっぱり相続したい」と思っても、その撤回や取消しはできません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申し立てを行うことで完了しますが、この申し立てには期限が設けられています。相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければならず、期限を過ぎると相続放棄が認められなくなります。
また、相続放棄を選択することで、相続財産に伴う負債や義務から解放される一方で、放棄した財産に対する権利も失うため、慎重な判断が求められます。
特に、相続財産に不動産や借金が含まれている場合、その内容を十分に理解した上で決定を下すことが大切です。相続放棄は一度行うと取り消せないため、後悔のないようにしっかりと考えましょう。
まとめ
相続放棄と国庫帰属の手続きについて、さまざまなポイントを解説してきました。相続土地国庫帰属制度は、使い道のない土地を手放すための有効な手段ですが、申請には厳格な審査が伴います。
法務局への相談から始まり、必要な書類の作成・提出、承認後の負担金の納付といった一連の流れを理解しておくことが重要です。
また、国庫帰属が認められない土地の種類についても注意が必要です。建物が存在する土地や担保権が設定されている土地などは、国庫帰属の対象外となるため、事前に確認しておくことが求められます。
さらに、相続放棄を行う際の注意点として、手続きの期限や撤回の不可についても理解しておくことが大切です。
このように、相続放棄と国庫帰属の手続きには多くの要素が絡んでいますが、正しい情報をもとに行動することで、負担を軽減し、スムーズな手続きを実現することが可能です。相続に関する不安を解消するために、ぜひ本記事を参考にしていただければと思います。
横浜市で口コミ1位の葬儀社である横浜葬儀社はばたきグループの運営するメディア「葬儀の豆知識」内の記事「【2025年最新版】信頼できるライフエンディング情報サイト・サービスまとめ」に当社が掲載されました。



