生前に相続放棄の手続きはできない?生前にできることを解説!
生前に相続放棄の手続きをしたいと考える方は多いものの、家庭裁判所では受理されません。それでも将来の相続トラブルを防ぐ準備は可能です。
本記事では、推定相続人の廃除請求や遺言書による財産配分指定、債務整理や生命保険の受取人設定など、生前に実践できる対策を時系列で整理し、家族間トラブルと税負担を最小限に抑える方法を解説します。早めに備えて家族の安心につなげましょう。
生前に相続放棄の手続きはできない
相続放棄は、相続が開始された後に行う手続きであり、生前にその手続きを行うことはできません。相続放棄は、相続人が相続財産を受け取らないことを選択するもので、主に債務が多い場合や、相続トラブルを避けたい場合に利用されます。
しかし、家庭裁判所は生前の相続放棄を受理しないため、相続が発生する前にこの手続きを済ませることは不可能です。
このため、生前に相続放棄を考える場合は、他の方法で将来の相続トラブルを未然に防ぐ必要があります。例えば、遺言書を作成することで、財産の配分を明確にし、相続人間の争いを避けることができます。
また、推定相続人の廃除請求を行うことで、特定の相続人を相続から排除することも可能です。これらの対策を講じることで、相続開始後の混乱を最小限に抑えることができるでしょう。
生前にできる準備を整えることで、家族にとって安心できる相続を実現することが重要です。相続放棄ができないことを理解した上で、他の手段を検討し、適切な対策を講じることが求められます。
生前に相続放棄のためにできることとは

生前に相続放棄を希望する場合、直接的な手続きはできませんが、相続トラブルを未然に防ぐための対策はいくつか存在します。これから解説する手段を活用することで、将来的な相続に関する問題を軽減し、家族の安心を確保することが可能です。
推定相続人の廃除請求をする
相続放棄が生前に行えないことを理解した上で、相続トラブルを未然に防ぐための手段として「推定相続人の廃除請求」があります。この手続きは、特定の相続人が相続権を失うことを目的としたもので、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
推定相続人の廃除請求は、主に相続人が故人に対して重大な不正行為を行った場合や、家庭内での不和が原因で相続権を剥奪したい場合に利用されます。
例えば、相続人が故人に対して虐待を行ったり、遺産を不正に取得しようとした場合などが該当します。この請求が認められると、該当する相続人は相続権を失い、遺産分割から除外されることになります。
ただし、廃除請求は簡単に行えるものではなく、裁判所に対して十分な証拠を提出する必要があります。また、廃除請求が認められるかどうかは、裁判所の判断に委ねられます。そのため、事前に法律の専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
遺言状の作成をする
遺言は、生前に相続人間の利害を調整し、紛争を未然に防ぐ最も基本的な手段です。形式には自筆証書遺言と公正証書遺言があり、自筆証書は全文を自書し日付・署名を添えることで成立しますが、方式不備や紛失リスクが課題です。
2020年7月10日からは法務局による自筆証書遺言保管制度が始まり、保管証明書を相続手続きで利用できるようになったため、使い勝手が向上しました。
一方、公正証書遺言は公証人が内容を確認し、原本を公証役場で保管するため、方式不備で無効となる心配がほぼありません。費用は財産評価額に応じ数万円〜数十万円ですが、将来の訴訟コストや家族の精神的負担を考えれば十分に回収可能です。
いずれの方式でも、財産目録を添付し、特定財産の帰属理由を説明しておくと相続人の理解が進みます。
また、法定相続人の遺留分(配偶者・直系卑属・直系尊属)を侵害しないよう配分を設計し、必要に応じて付言事項で介護の労や教育費負担など感謝の意を記すと、感情的対立も緩和できます。
遺言書を書く時の注意点とは
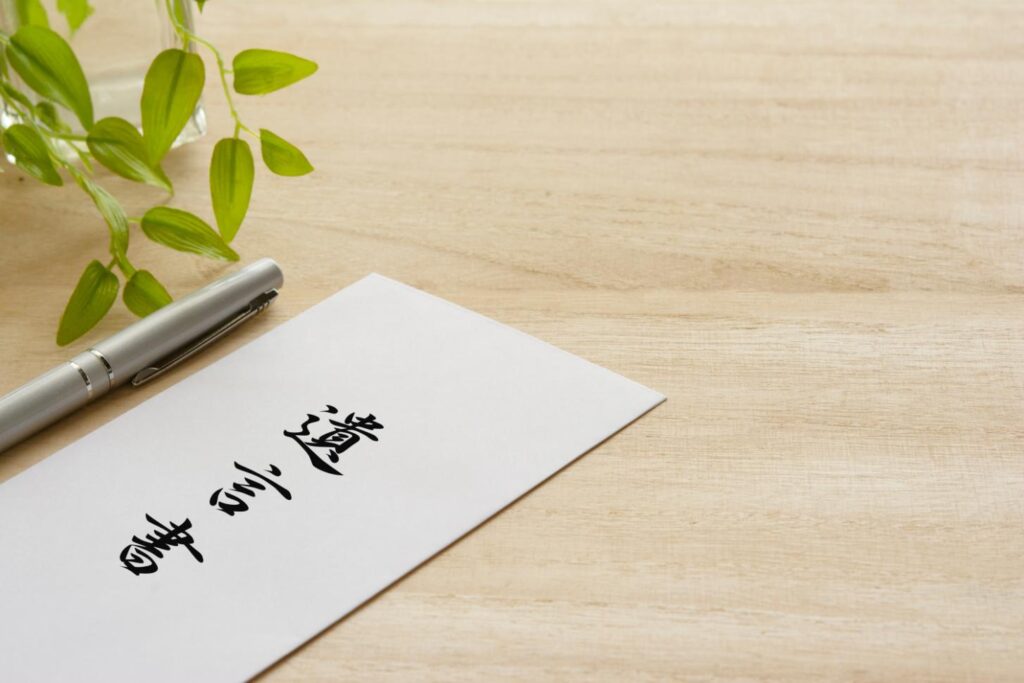
遺言書を書くときにはいくつか注意すべきポイントがあります。このセクションで解説する注意点を踏まえ、遺言書を書いていきましょう。
家族に遺言書を作成したことや保管場所を伝える
遺言書を作成することは、将来の相続トラブルを避けるための重要なステップです。しかし、遺言書が存在することやその保管場所を家族に伝えておくことも同様に重要です。
なぜなら、遺言書が作成されていても、相続人がその存在を知らなければ、意図した通りに財産が分配されない可能性があるからです。まず、遺言書を作成したことを家族に知らせることで、相続が発生した際にスムーズに手続きを進めることができます。
特に、遺言書が家庭裁判所での検認を必要とする場合、相続人がその存在を知らなければ、手続きが遅れることになります。したがって、遺言書の作成後は、信頼できる家族にその旨を伝え、必要に応じて内容についても話し合うことが望ましいでしょう。
次に、遺言書の保管場所を明確にしておくことも大切です。遺言書は、金庫や信託銀行、または専門家に預けることが一般的ですが、どこに保管しているのかを家族に伝えておくことで、相続発生時に探し回る手間を省くことができます。
保管場所を知らないと、遺言書が見つからず、法定相続に従った分配が行われることになり、遺言者の意向が反映されない結果となることもあります。
遺留分について検討しておく
遺留分とは、相続人が法定相続分の一部を必ず受け取る権利のことを指します。これは、遺言書によって財産の配分が指定されている場合でも、相続人が最低限受け取ることができる財産の割合を保障するための制度です。
遺留分は、相続人の権利を守る重要な要素であり、特に生前に遺言書を作成する際には、しっかりと検討しておく必要があります。
遺留分の割合は、相続人の人数や関係性によって異なります。例えば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者の遺留分は相続財産の1/2、子どもたちの遺留分はそれぞれ相続財産の1/4となります。このように、遺留分を考慮することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。これにより、遺言書に記載された内容が無効になる可能性もあるため、遺言書を作成する際には、遺留分について十分に理解し、配慮することが重要です。
財産内容はできるだけ詳細に書いておく
遺言書を作成する際には、財産内容をできるだけ詳細に記載することが重要です。具体的には、所有している不動産や預貯金、株式、貴金属、その他の資産について、種類や数量、評価額などを明確に記載することが求められます。
これにより、遺族が遺言書をもとにスムーズに相続手続きを進めることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。また、財産の詳細を記載することで、相続人がどのように財産を分配されるのかを理解しやすくなります。
特に、特定の相続人に特定の財産を譲る場合は、その旨を明確に記載することが大切です。例えば、「〇〇不動産は長男に、△△預金は次男に」といった具体的な指示を盛り込むことで、相続人間の誤解や争いを避けることができます。
さらに、財産の評価額を記載することも有効です。これにより、相続税の計算や遺産分割の際に役立ちます。評価額が不明な場合は、専門家に相談して適切な評価を受けることをお勧めします。
家族に財産を残す方法とは

家族に財産を残すためには、いくつかの方法があります。これから解説する方法を組み合わせることで、家族の将来をより安心なものにすることができるでしょう。
自己破産などの債務整理をする
生前に相続放棄を考える際、債務整理は重要な手段の一つです。特に自己破産は、相続人が負うべき債務を大幅に軽減することができるため、将来の相続トラブルを未然に防ぐ効果があります。自己破産を行うことで、借金の返済義務が免除され、相続時に残る負債を減らすことができます。
自己破産の手続きは、裁判所に申し立てを行うことで開始されます。申し立てが受理されると、債務者の財産が整理され、債権者への支払いが免除されることになります。
ただし、自己破産には一定の条件があり、資産や収入の状況によっては適用されない場合もありますので、事前に専門家に相談することが重要です。
また、自己破産以外にも、任意整理や特定調停といった債務整理の方法があります。これらの方法では、債権者との交渉を通じて返済条件を見直し、負担を軽減することが可能です。これにより、相続時に残る負債を減らし、家族に対する経済的な負担を軽減することができます。
生命保険に加入をして家族に財産を残す
生命保険は、相続に関するトラブルを避けるための有効な手段の一つです。特に、相続放棄を考えている場合でも、生命保険を利用することで、家族に確実に財産を残すことができます。
生命保険の受取人を指定することで、保険金は遺産分割の対象外となり、相続人間の争いを避けることができるのです。
生命保険に加入する際は、受取人を明確に設定することが重要です。受取人を配偶者や子供に指定することで、万が一の際に迅速に保険金が支払われ、家族の生活を支える資金となります。また、保険金は相続税の課税対象となりますが、相続財産とは別に扱われるため、相続税対策としても有効です。
さらに、生命保険にはさまざまな種類があり、定期保険や終身保険、養老保険など、自分のニーズに合わせて選ぶことができます。特に、終身保険は死亡時に必ず保険金が支払われるため、長期的な視点で家族の安心を確保する手段として人気があります。
生前贈与を活用する
生前贈与は、相続対策として非常に有効な手段の一つです。相続が発生する前に、自分の財産を家族や親しい人に贈与することで、将来的な相続トラブルを未然に防ぐことができます。また、生前贈与を行うことで、相続税の負担を軽減することも可能です。
生前贈与には、贈与税がかかる場合がありますが、年間110万円までの贈与については非課税となるため、計画的に贈与を行うことで、税負担を抑えることができます。
例えば、毎年少しずつ贈与を行うことで、贈与税の課税対象を避けることができ、結果的に相続財産を減少させることができます。
さらに、生前贈与は、贈与を受ける側にとっても大きなメリットがあります。特に、若い世代に資金を渡すことで、教育資金や住宅購入資金として活用してもらうことができ、家族全体の経済的な安定を図ることができます。
ただし、生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にすることが重要です。また、贈与を受けた側がその財産をどのように扱うかについても考慮する必要があります。
相続放棄の注意点とは

相続放棄を考える際には、いくつかの重要な注意点があります。これから解説するいくつかの注意点を踏まえ、相続放棄を行いましょう。
相続開始から3ヶ月以内の期限内に手続きを完了させる
相続放棄を考える際には、手続きの期限が非常に重要です。相続が開始した日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行わなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められなくなります。相続開始とは、被相続人が亡くなった日を指し、その日からカウントが始まります。
この3ヶ月という期間は、相続人が被相続人の財産や負債の状況を把握し、相続放棄をするかどうかを判断するための猶予期間でもあります。相続放棄を選択する場合、相続人はその後の手続きや財産の管理から解放されるため、特に負債が多い場合には重要な選択肢となります。
ただし、相続放棄の手続きを行う際には、必要な書類を準備し、家庭裁判所に提出する必要があります。これには、相続放棄申述書や戸籍謄本などが含まれます。手続きが煩雑であるため、早めに行動を起こすことが推奨されます。
一度放棄すると原則として撤回できない
相続放棄は、相続人が故人の遺産を受け取らないことを選択する手続きですが、一度この手続きを行うと、原則として撤回することはできません。
これは、相続放棄が法的に確定した行為であり、他の相続人や債権者に対しても影響を及ぼすためです。したがって、相続放棄を決断する際には慎重に考える必要があります。
相続放棄を行う理由としては、故人が多額の債務を抱えていた場合や、相続財産がマイナスである場合が一般的です。
しかし、相続放棄を選択した後に、状況が変わってプラスの財産が発生した場合でも、放棄したことによってその財産を受け取ることはできません。このため、相続放棄を行う前に、相続財産の内容を十分に確認し、将来的なリスクを考慮することが重要です。
また、相続放棄の手続きは、相続開始から3ヶ月以内に行わなければならないため、時間的な制約もあります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなり、相続財産を受け取る義務が生じることになります。
遺産を処分すると相続放棄できなくなる可能性がある
相続放棄を考える際には、遺産の処分に関して十分な注意が必要です。相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで成立しますが、この期間内に遺産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
具体的には、相続財産を売却したり、譲渡したりする行為は、相続放棄の意思を示すものとは見なされず、結果として相続を受け入れたと判断されることがあります。
このため、相続放棄を検討している場合は、まずは遺産の状況をしっかりと把握し、無用な処分を避けることが重要です。特に、負債が多い場合や、相続財産がマイナスの価値を持つ場合には、早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが求められます。
相続放棄を行うことで、将来的な負担を軽減し、家族の安心を守るための重要なステップとなりますので、慎重に行動することが大切です。
相続放棄しても保険金や遺族年金はもらえる
相続放棄を選択した場合でも、保険金や遺族年金を受け取ることができる点は重要です。相続放棄とは、相続人が故人の遺産を受け取らないことを選ぶ手続きですが、これはあくまで故人の遺産や負債に対する権利を放棄するものであり、特定の給付金や年金に対する権利には影響を及ぼしません。
例えば、生命保険の受取人が指定されている場合、相続放棄を行ってもその保険金は受け取ることができます。これは、生命保険が相続財産とは別のものであり、契約に基づく給付金だからです。
したがって、相続放棄を選んだとしても、家族の生活を支えるための資金を確保する手段として、生命保険は非常に有効です。
また、遺族年金についても同様です。遺族年金は、故人が加入していた年金制度に基づく給付であり、相続放棄の影響を受けません。これにより、相続放棄を選択した場合でも、遺族年金を受け取ることで、生活の安定を図ることが可能です。
このように、相続放棄を行った場合でも、保険金や遺族年金を受け取る権利が残るため、家族の経済的な支援を受ける手段を確保することができます。相続に関する選択肢を理解し、適切な対策を講じることで、将来の不安を軽減することができるでしょう。
まとめ
相続放棄は生前に行うことができないため、将来の相続トラブルを未然に防ぐためには、他の手段を講じることが重要です。推定相続人の廃除請求や遺言書の作成、債務整理、生命保険の受取人設定など、さまざまな対策を通じて、家族の安心を確保することが可能です。
特に、遺言書は自分の意思を明確に示す手段として非常に有効です。遺言書を作成する際には、家族にその存在や保管場所を伝えることが大切です。また、遺留分についても考慮し、財産内容を詳細に記載することで、後のトラブルを避けることができます。
さらに、自己破産などの債務整理や生前贈与を活用することで、家族に対する負担を軽減し、円滑な相続を実現することができます。相続放棄の手続きには注意が必要ですが、適切な準備を行うことで、家族の未来を守ることができるのです。
このように、生前にできる対策を講じることで、相続に関する不安を軽減し、家族間のトラブルを最小限に抑えることができます。早めの備えが、安心した未来につながることを忘れないようにしましょう。



