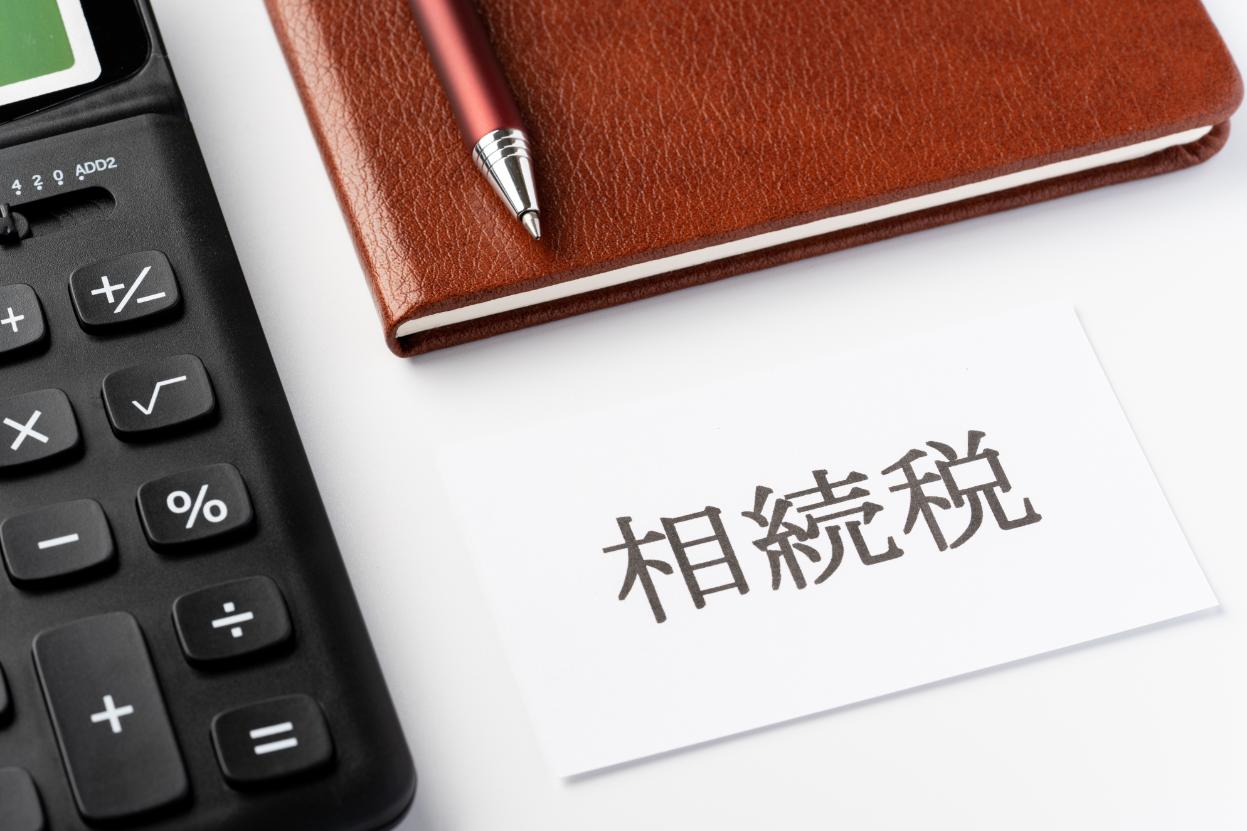相続時精算課税制度の手続きとは?メリットや注意点を解説!
相続時精算課税制度を選択すると、贈与税申告書と選択届出書を税務署に提出するだけで2,500万円まで贈与税が非課税になります。ただし暦年贈与が使えなくなるなどデメリットもあり、慎重な判断が必要です。
本記事では、選択条件、申告書作成の手順、メリットとデメリットの比較、不動産や金融資産を組み合わせた相続税対策のシミュレーションを詳しく解説します。制度活用のヒントにしてください。
相続時精算課税制度の手続きとは

相続時精算課税制度を利用するには、初回の贈与を受けた翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」とその年分の贈与税申告書を同時に提出する必要があります。贈与者は贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母等、受贈者は18歳以上の直系卑属であることが要件です。
戸籍謄本や贈与契約書を添付し、e-Taxで申告できます。選択後は同じ贈与者について暦年課税へ戻せないため、一度切りの選択と理解してください。
累積課税価格が2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税が課されます。2024年改正で基礎控除110万円が追加されたものの、相続時には控除後残額を相続財産へ加算して税額を精算します。
さらに、土地・株式・現金など財産種類は問わず、贈与回数も無制限ですが、長期的な資金計画と相続税試算を照合したうえで選択することが重要です。
手続きの流れとしては、まず贈与者が選択届出書を作成し、税務署に提出します。その後、贈与税申告書を提出する際に、相続時精算課税制度を選択した旨を記載します。これにより、贈与税の非課税枠が適用されることになります。
相続時精算課税制度のメリットとは

累計2,500万円までの控除を受けられる
本制度では、生前贈与の累計額が2,500万円に達するまで贈与税が非課税となります。住宅購入資金や自社株承継など、多額資金をまとめて移転したい場合に節税効果が大きいです。
2024年改正により、制度を選択しても毎年110万円の基礎控除が新設されたため、枠を使い切った後も少額贈与を継続できます。非課税枠超過分には一律20%課税され、納付税額は後日相続税から控除されるため二重課税にはなりません。
さらに、贈与時価で相続財産に加算されるため、時価把握が容易な現金や上場株を優先すると管理が簡便です。制度は贈与者ごとに終生変更できないため、贈与額とタイミングを専門家と設計し、累計管理表を保管して課税漏れを防ぐ必要があります。
ただし、2,500万円の非課税枠を超えた場合には、超過分に対して贈与税が課税されるため、計画的な贈与が求められます。また、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与の非課税枠(110万円)が利用できなくなるため、慎重に判断することが重要です。
早い段階で財産を引き継げる
相続時精算課税制度の大きなメリットの一つは、早い段階で財産を引き継ぐことができる点です。この制度を利用することで、贈与者が生前に財産を受け取ることが可能となり、相続が発生する前に資産を移転することができます。
これにより、受贈者は早期に財産を手に入れることができ、将来的な相続税の負担を軽減することが期待できます。
特に、子どもや孫に対して資産を贈与する場合、相続時精算課税制度を利用することで、贈与税が非課税となる2,500万円の枠内で財産を移転できるため、計画的な資産管理が可能になります。
また、早期に財産を引き継ぐことで、贈与者自身も安心感を得ることができます。自分の財産がどのように使われるかを見守ることができるため、贈与者にとっても精神的なメリットがあります。
贈与者ごとに制度を選択できる
相続時精算課税制度の大きな特徴の一つは、贈与者ごとに制度を選択できる点です。これにより、家族の状況や財産の種類に応じて、最も有利な方法を選ぶことが可能になります。
例えば、親が子どもに対して贈与を行う場合、親がこの制度を選択することで、2,500万円までの贈与が非課税となります。一方で、他の親族が贈与を行う場合には、別の選択をすることもできるため、柔軟な対応が可能です。
この制度を利用することで、贈与者は自分の財産を計画的に移転することができ、相続時の負担を軽減することができます。
また、贈与を受ける側も、早い段階で財産を受け取ることができるため、将来的な相続税の負担を軽減することが期待できます。ただし、選択した制度によっては、他の贈与税の非課税枠が使えなくなるため、慎重な判断が求められます。
このように、相続時精算課税制度は贈与者ごとに選択できるため、家族全体の財産管理や相続計画において非常に有効な手段となります。
相続時精算課税制度の注意点とは

相続時精算課税制度にはいくつかの注意点があります。これから解説する点を理解し、適切な判断を行うことが重要です。
暦年贈与(贈与税の非課税枠110万円)が使えない
相続時精算課税を選ぶと、基礎控除110万円を利用した暦年贈与が二度と使えません。たとえば学費や生活費を毎年少額で支援して税負担を分散する手法が封じられ、2年目以降の1円の贈与でも申告が必須になります。
累積額が2,500万円を超えると超過部分に一律20%課税されるため、納税資金の準備が欠かせません。2024年改正で110万円の控除が部分的に導入されましたが、申告後に差し引く方式のため事務負担は残ります。
さらに、選択届出は初回贈与の翌年3月15日が期限で取り消し不可なので、家族の資金需要や相続税試算を踏まえ、10年以上の長期計画で制度を選択する必要があります。
このため、相続時精算課税制度を選択する際には、贈与のタイミングや金額を慎重に考える必要があります。特に、将来的に贈与を行う予定がある場合、暦年贈与を利用することで、長期的に見て税負担を軽減できる可能性があるため、制度の選択は慎重に行うべきです。
贈与した財産の価値が下がっていると損をする
相続時精算課税制度を利用する際には、贈与した財産の価値が下がるリスクを十分に理解しておくことが重要です。この制度では、贈与した財産の評価額が将来的に相続税の計算に影響を与えるため、贈与時点での価値が低下してしまうと、結果的に損をする可能性があります。
例えば、不動産を贈与した場合、その不動産の市場価値が下がると、相続時にその価値を基に相続税が計算されるため、贈与時に期待していた控除額が実現できなくなることがあります。
また、金融資産においても同様で、株式や投資信託の価値が下がると、贈与時に受けた非課税枠を十分に活用できないことになります。
このようなリスクを避けるためには、贈与を行うタイミングや対象となる財産の選定が重要です。市場の動向を見極め、価値が安定している資産を選ぶことが、相続時精算課税制度を利用する際の賢い戦略となります。
孫は相続税が2割増しになる
相続時精算課税制度を利用する際の注意点の一つとして、孫に対する相続税が通常よりも2割増しになるという点があります。この制度を選択すると、贈与者が亡くなった際に、孫が受け取る財産に対して相続税が高くなる可能性があるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
具体的には、相続税は通常、相続財産の評価額に基づいて計算されますが、相続時精算課税制度を利用した場合、孫が受け取る財産に対しては、相続税の税率が引き上げられることになります。これにより、相続税の負担が増加し、結果的に孫が受け取る金額が減少することになります。
このような影響を考慮すると、孫に対して贈与を行う際には、相続税の負担を軽減するための対策を講じることが求められます。
例えば、贈与のタイミングや金額を調整することで、相続税の負担を最小限に抑えることが可能です。また、孫に対する贈与を行う際には、他の相続人とのバランスを考慮することも大切です。
相続時精算課税制度を利用する際には、孫に対する相続税の増加というリスクをしっかりと認識し、適切な対策を講じることが、将来的なトラブルを避けるための鍵となります。
効果的な相続税対策とは

相続税対策にはさまざまな方法があります。これから解説する対策を組み合わせることで、より効果的な相続税対策が実現します。
生命保険を契約しておく
相続税対策の一環として、生命保険の契約は非常に有効な手段です。生命保険は、被保険者が亡くなった際に保険金が支払われるため、相続人にとっては即座に現金を得ることができるメリットがあります。この現金は、相続税の支払いに充てることができるため、相続税の負担を軽減する助けとなります。
さらに、生命保険の保険金には非課税枠が設けられており、一定の金額までは相続税がかからないため、相続人にとっては非常に魅力的です。
具体的には、保険金の受取人が配偶者や子どもである場合、500万円×法定相続人の数までが非課税となります。この制度を利用することで、相続税の負担を大幅に減少させることが可能です。
また、生命保険は契約者が生前に保険料を支払うことで、相続時に発生する現金の準備を行うことができます。これにより、相続人が相続税の支払いに困ることなく、スムーズに財産を引き継ぐことができるのです。
このように、生命保険を活用することで、相続税対策を効果的に行うことができるため、早めに契約を検討することをお勧めします。
生前贈与も検討しておく
生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段の一つです。相続時精算課税制度を利用する際には、贈与を行うタイミングや方法を慎重に考えることが重要です。生前贈与を行うことで、相続財産を減少させ、結果的に相続税の負担を軽減することが可能になります。
特に、贈与税の非課税枠を活用することで、毎年一定額を贈与することができ、これにより相続時の財産評価を下げることができます。例えば、暦年贈与を利用すれば、年間110万円までの贈与は非課税となります。この制度を利用することで、長期的に見れば大きな節税効果が期待できるでしょう。
また、生前贈与は受贈者にとってもメリットがあります。早い段階で財産を受け取ることで、将来の生活資金や教育資金に充てることができ、経済的な安定を図ることができます。
さらに、贈与者が元気なうちに贈与を行うことで、贈与者自身がどのように財産を分配したいかを明確にすることができ、家族間のトラブルを避けることにもつながります。
ただし、生前贈与には注意点もあります。贈与した財産が将来的に価値を失った場合、贈与者が損をする可能性があるため、慎重な判断が求められます。
不動産評価額を下げる
不動産の評価額を下げることは、相続税対策において非常に重要なポイントです。相続税は、相続財産の評価額に基づいて課税されるため、評価額を適切に管理することで税負担を軽減することが可能です。具体的には、以下の方法が考えられます。
まず、土地や建物の評価額を下げるためには、適正な評価方法を選ぶことが重要です。例えば、相続税評価額は路線価や固定資産税評価額に基づいて算出されますが、これらの評価額は市場価格とは異なる場合があります。
次に、土地の利用方法を見直すことも効果的です。例えば、農地や山林などの特例を利用することで、評価額を大幅に下げることができます。また、賃貸物件として運用することで、収益を上げつつ評価額を抑えることも可能です。
さらに、建物の老朽化や改修工事を行うことで、評価額を調整することも考えられます。特に、耐震補強や省エネ改修を行うことで、評価額が下がるだけでなく、将来的な資産価値の向上にもつながります。
死亡退職金の非課税枠を活用する
死亡退職金は、被保険者が亡くなった際に支給される退職金であり、相続税の課税対象外となる非課税枠が設けられています。
この非課税枠は、受取人が受け取る金額に対して適用されるため、相続税対策として非常に有効です。具体的には、死亡退職金の非課税枠は、受取人の人数に応じて計算され、1人あたり500万円が非課税となります。
例えば、被保険者が亡くなり、配偶者と子どもが受取人の場合、配偶者には500万円、子どもにはそれぞれ500万円の非課税枠が適用されるため、合計で1,500万円までの死亡退職金が非課税となります。この制度を利用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
ただし、死亡退職金を受け取る際には、受取人の選定や金額の設定に注意が必要です。受取人が多いほど非課税枠が拡大するため、家族構成や受取人の選定を考慮した上で、計画的に活用することが重要です。
また、死亡退職金の受取人を指定する際には、遺言書を作成することも一つの方法です。これにより、受取人の意向を明確にし、相続時のトラブルを避けることができます。
財産の分割方法の工夫により税額を軽減する
相続税対策において、財産の分割方法を工夫することは非常に重要です。適切な分割を行うことで、相続税の負担を軽減し、相続人間のトラブルを避けることができます。まず、財産をどのように分割するかを考える際には、各相続人の状況やニーズを考慮することが大切です。
例えば、相続人の中に住宅ローンを抱えている人がいる場合、その人に不動産を相続させることで、相続税の負担を軽減することができます。また、金融資産についても、相続人の生活状況に応じて分配することで、相続税の負担を分散させることが可能です。
さらに、相続税の基礎控除を最大限に活用するためには、財産の評価額を下げる工夫も必要です。例えば、不動産の評価額を下げるために、賃貸物件として運用することや、共有名義にすることも一つの方法です。これにより、相続税の課税対象となる財産の評価額を抑えることができます。
このように、財産の分割方法を工夫することで、相続税の負担を軽減し、相続人全員が納得できる形での相続を実現することが可能です。相続税対策は早めに計画を立てることが重要ですので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。
まとめ
相続時精算課税制度は、贈与税の負担を軽減し、早期に財産を引き継ぐための有効な手段です。特に、2,500万円までの贈与が非課税となる点は大きな魅力ですが、暦年贈与の非課税枠が使えなくなるなどのデメリットも存在します。
制度を利用する際は、選択条件や申告手続き、メリット・デメリットをしっかりと理解し、自身の状況に合った判断を行うことが重要です。
また、相続税対策としては、生命保険の活用や生前贈与、不動産評価の見直しなど、さまざまな方法があります。
これらを組み合わせることで、より効果的な相続税対策を講じることが可能です。相続に関する知識を深め、計画的に準備を進めることで、将来の負担を軽減し、円滑な相続を実現しましょう。