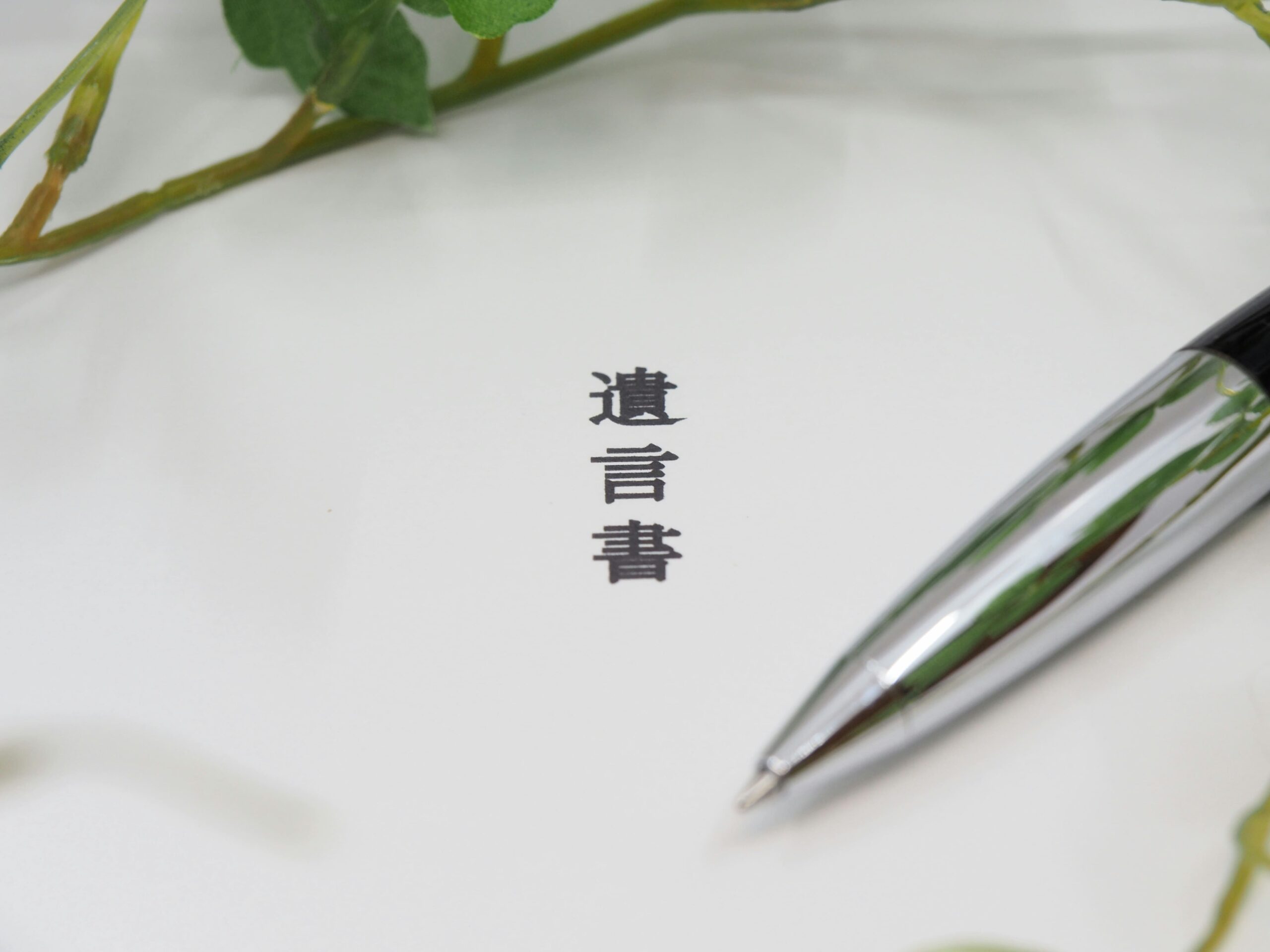法務局でできる自筆証書遺言書保管制度とは?保管の流れを解説
作成した自筆証書遺言を確実に守りたいなら、法務局で利用できる保管制度を検討しましょう。遺言書を預ければ家庭裁判所での検認が不要になり、紛失や改ざんの心配も軽減できます。
本記事では、保管申請の予約方法、必要書類、当日の流れから保管証の受け取り、保管後の閲覧請求や内容変更時の手続きまでをわかりやすく解説します。
法務局でできる自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月施行の改正相続法で創設された公的サービスで、法務局が遺言者から原本を受け取り高精度スキャンと併せて150年間厳重保管することで、紛失・改ざん・偽造リスクを根本的に抑えます。
申請はネットまたは電話予約のうえ、遺言者本人が無封の遺言書と本人確認書類、手数料3,900円を持参し窓口で手続きを行います。職員が全文自書・日付・署名押印・訂正方式を形式審査するため、方式不備による無効リスクが大幅に低減されます。
保管後は、遺言書の閲覧・差替え・撤回が自由にでき、相続開始時には相続人へ遺言の存在が自動通知されます。さらに、検認不要の遺言書情報証明書(交付1,400円)を用いるだけで銀行解約や不動産登記が即時処理でき、手続きコストと時間を劇的に短縮できる点が最大のメリットです。
さらに、住所や氏名が変わった際も届出一枚でデータ更新が可能で、マイナポータル経由の証明書請求にも対応しているため、遠方在住の相続人でもオンラインで完結できます。
自筆証書遺言書とは
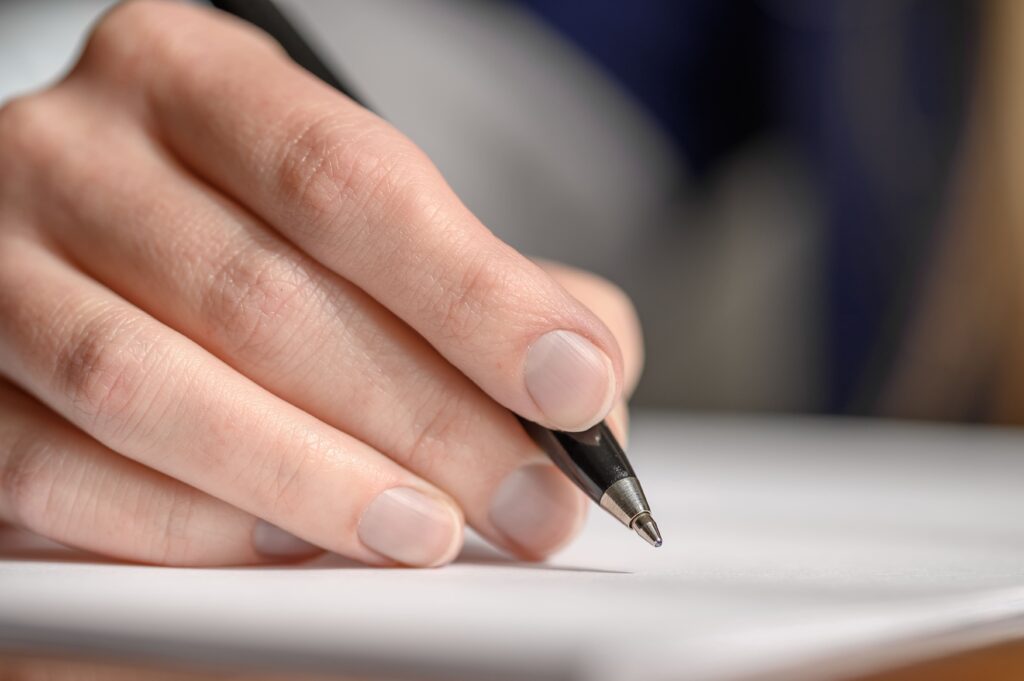
自筆証書遺言書とは、遺言者が自らの手で書いた遺言のことを指します。この遺言書は、遺言者の意思を直接反映したものであり、法的に有効な文書として認められています。自筆証書遺言は、特に遺言者が自分の財産の分配や相続人に対する意向を明確に示すための重要な手段となります。
自筆証書遺言の特徴として、遺言者が全ての内容を自筆で記入する必要がある点が挙げられます。これにより、遺言者の真意が伝わりやすく、他者による改ざんのリスクも低減されます。また、特別な形式や手続きが不要であるため、比較的簡単に作成できるのも大きな魅力です。
ただし、自筆証書遺言には注意点もあります。例えば、遺言書が適切に作成されていない場合、無効とされることがあります。
そのため、法律に基づいた正しい書き方や必要な要素を理解しておくことが重要です。自筆証書遺言を作成する際は、内容を明確にし、誤解を招かないようにすることが求められます。
自筆証書遺言書のメリットとは

自筆証書遺言書には多くのメリットがあります。これから解説するメリットを理解することで、より安心して遺言書を作成することができます。
費用がかからない
自筆証書遺言書の最大の魅力の一つは、費用がかからない点です。遺言書を自分で作成する場合、特別な手数料や専門家への報酬を支払う必要がありません。
必要なのは、紙とペンだけであり、誰でも手軽に始めることができます。このため、経済的な負担を気にすることなく、自分の意思をしっかりと残すことが可能です。
さらに、法務局での保管制度を利用する際も、保管手数料は非常にリーズナブルです。遺言書を法務局に預けることで、家庭裁判所での検認手続きが不要になるため、結果的に時間や費用の節約にもつながります。
このように、自筆証書遺言書は、経済的な観点からも非常に優れた選択肢であり、誰でも気軽に利用できる制度であることがわかります。
他者に遺言内容を知られない
自筆証書遺言書を法務局に保管する大きなメリットの一つは、遺言内容が他者に知られることがない点です。通常、遺言書は作成者の意向を反映した重要な文書であり、その内容が他人に知られることは望ましくありません。
法務局での保管制度を利用することで、遺言書は厳重に管理され、外部の人間がアクセスすることはできません。
この制度を利用することで、遺言書の内容が相続人や他の関係者に知られることなく、作成者の意図を尊重した形で保管されます。特に、遺言書に記載された内容が相続に関する重要な決定を含む場合、他者に知られることはトラブルの原因となることがあります。
また、遺言書の保管が法務局で行われることで、遺言書の改ざんや偽造のリスクも低減します。法務局は公的機関であり、信頼性の高い管理が行われるため、安心して遺言書を預けることができます。
作成までに時間がかからない
自筆証書遺言書の作成は、比較的短時間で行えるため、多忙な方にも適しています。遺言書は特別な形式や手続きが必要なく、自分の意思をそのまま書き記すことができるため、思いついたときにすぐに作成することが可能です。
また、法務局での保管制度を利用することで、作成した遺言書を安全に保管できるため、安心して作成に取り組むことができます。
遺言書の作成にあたっては、法律的な知識がなくても、自分の思いや希望を自由に表現できるため、時間をかけずに自分の意志を形にすることができるのです。
このように、自筆証書遺言書は手軽に作成できるため、急な状況や思い立ったときにすぐに対応できる点が大きな魅力です。特に、遺言書を作成することを考えている方にとって、時間的な負担が少ないことは大きな利点と言えるでしょう。
自筆証書遺言を法務局に保管する流れ

自筆証書遺言を法務局に保管するための流れは、いくつかのステップに分かれています。これから解説する一連の流れを理解することで、スムーズに手続きを進めることができます。
自筆証書遺言を作成する
自筆証書遺言を作成することは、遺言者自身の意思を明確に示す重要なステップです。この遺言書は、遺言者が自ら手書きで作成するものであり、法律的にも有効な文書として認められています。
まず、遺言書には遺言者の氏名、住所、作成日、そして具体的な遺言内容を記載する必要があります。特に、遺産の分配方法や特定の財産を誰に譲るかといった詳細を明確にすることが重要です。
作成にあたっては、遺言者自身が全ての内容を手書きすることが求められます。パソコンや印刷物を使用することはできず、手書きであることが自筆証書遺言の条件です。
また、遺言書の内容が不明瞭であったり、誤解を招く表現が含まれていると、後々トラブルの原因になることがありますので、注意が必要です。
さらに、遺言書を作成する際には、法律に基づいた形式を守ることが求められます。例えば、遺言者の署名や押印が必要です。これらの要件を満たすことで、遺言書の有効性が確保され、法務局での保管手続きもスムーズに進むでしょう。
遺言書の保管場所を決める
自筆証書遺言書を法務局に保管する際には、まず遺言書の保管場所を決める必要があります。法務局では、全国の各地にある支局や出張所で遺言書の保管が可能ですが、どの場所に保管するかは慎重に考えるべきです。
自宅からのアクセスの良さや、利用する法務局の混雑具合などを考慮し、自分にとって最も便利な場所を選ぶことが重要です。
また、保管場所を決める際には、遺言書を保管する法務局の所在地が、相続人や関係者にとってもアクセスしやすいかどうかも考慮しましょう。遺言書の保管後、相続手続きが行われる際に、相続人がスムーズに手続きを進められるようにするためです。
さらに、保管場所を選ぶ際には、法務局のサービスや対応の質も確認しておくと良いでしょう。各法務局によって、遺言書の保管に関するサポートや相談窓口の充実度が異なるため、事前に情報を収集しておくことをお勧めします。
遺言書の保管申請書を作成する
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうためには、保管申請書を作成する必要があります。この申請書は、遺言書の保管を希望する旨を正式に伝えるための重要な書類です。
まず、申請書には遺言者の氏名、住所、生年月日などの基本情報を正確に記入します。また、遺言書の内容についても簡潔に記載することが求められます。
申請書のフォーマットは法務局の公式ウェブサイトからダウンロードできるため、必要に応じて印刷して利用しましょう。
記入が完了したら、必要書類とともに持参することになります。申請書の記入にあたっては、誤字脱字がないように注意し、特に氏名や住所の表記に間違いがないか再確認することが大切です。
さらに、申請書には遺言書の保管を希望する理由や、遺言書の作成日なども記載することが推奨されます。これにより、法務局側での手続きがスムーズに進むことが期待できます。
保管申請の予約・申請を行う
自筆証書遺言書を法務局に保管するためには、まず保管申請の予約を行う必要があります。予約は、法務局の窓口または電話で行うことができ、事前に日時を決めておくことでスムーズに手続きを進めることができます。予約の際には、遺言書の内容や保管を希望する法務局の所在地を伝えることが求められます。
予約が完了したら、指定された日時に法務局に出向きます。持参するものとしては、自筆証書遺言書そのもののほか、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。また、遺言書の保管申請書も事前に作成しておくと良いでしょう。
当日は、法務局の窓口で申請書を提出し、遺言書を手渡します。窓口の職員が遺言書の内容を確認し、問題がなければ保管証を発行してもらえます。
この保管証は、遺言書が法務局に保管されていることを証明する重要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。これで、法務局での自筆証書遺言書の保管申請が完了します。
保管証を受け取る
自筆証書遺言書の保管申請が無事に完了すると、法務局から保管証が交付されます。この保管証は、遺言書が法務局に安全に保管されていることを証明する重要な書類です。保管証を受け取る際には、申請時に提示した本人確認書類を再度持参する必要がありますので、忘れずに準備しておきましょう。
保管証には、遺言書の保管番号や保管日などの情報が記載されています。この情報は、遺言書の内容を確認したり、必要に応じて閲覧請求を行う際に必要となります。したがって、保管証は大切に保管しておくことが重要です。
また、保管証を受け取った後は、遺言書の内容を変更したい場合や新たに遺言書を作成したい場合にも、法務局での手続きが必要です。
保管証を持参することで、スムーズに手続きを進めることができるため、常に手元に置いておくことをお勧めします。これにより、遺言書の管理がより安心で確実なものとなります。
自筆証書遺言を法務局に保管してもらうメリット

自筆証書遺言を法務局に保管することで得られるメリットは多岐にわたります。これから解説するメリットを理解し、自筆証書遺言を法務局に保管してもらう選択肢も念頭に置いておきましょう。
家庭裁判所での検認が不要になる
法務局で自筆証書遺言書を保管する最大のメリットの一つは、家庭裁判所での検認手続きが不要になることです。通常、自筆証書遺言を遺族が開封し、内容を確認するためには、家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
この手続きは、遺言書の内容が正当であることを確認するためのものであり、時間と手間がかかる場合があります。しかし、法務局に遺言書を保管することで、この検認手続きが省略されます。
遺言書が法務局に保管されている場合、遺言者が亡くなった際には、遺言書の存在が自動的に確認され、相続手続きがスムーズに進むことが期待できます。これにより、遺族は余計な手続きを行うことなく、遺言の内容に基づいて相続を進めることができるため、精神的な負担も軽減されます。
また、法務局での保管制度を利用することで、遺言書の内容が公的に認められるため、遺族間でのトラブルを避けることにもつながります。遺言書が法務局に保管されていることを証明する書類も発行されるため、遺族は安心して相続手続きを進めることができるのです。
紛失や隠匿、破棄などのリスクがない
自筆証書遺言を法務局に保管する最大のメリットの一つは、遺言書が紛失したり、隠匿されたり、破棄されるリスクが大幅に減少することです。
自宅や他の場所に保管している場合、家族や親しい友人に見つからないまま、遺言書が失われてしまう可能性があります。また、意図的に遺言書を隠したり、破棄したりする行為も考えられますが、法務局に保管することで、こうした心配を解消できます。
法務局では、遺言書が適切に保管され、必要な時に確実に取り出せる体制が整っています。これにより、遺言者の意思が尊重され、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、法務局に保管された遺言書は、遺言者が亡くなった後に自動的に相続人に通知されるため、遺言書の存在を知らずに相続手続きを進めてしまうリスクも軽減されます。
死後に相続人などに通知してもらえる
自筆証書遺言を法務局に保管する大きなメリットの一つは、遺言者が亡くなった際に相続人や関係者に対して遺言書の存在を通知してもらえることです。
通常、遺言書が存在することを知らない相続人が多い中、法務局に保管されている遺言書は、遺言者の死後に自動的に相続人に通知されるため、遺言の内容が確実に伝わります。
この通知は、法務局が遺言者の死亡を確認した後に行われるため、相続人は遺言書の存在を知ることができ、遺産分割の手続きがスムーズに進む可能性が高まります。
また、遺言書が法務局に保管されていることで、遺言の内容が改ざんされるリスクも低減され、相続人は安心して手続きを進めることができます。
このように、法務局での自筆証書遺言書保管制度は、遺言者の意志を尊重し、相続人に対しても配慮された制度であると言えるでしょう。
まとめ
法務局での自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を安全に保管し、相続に関するトラブルを未然に防ぐための有効な手段です。自筆証書遺言を法務局に預けることで、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減できます。
また、遺言書の保管を通じて、相続人に対しても適切に通知されるため、遺族の負担を軽減することができます。
本記事では、保管申請の流れや必要書類、保管後の手続きについて詳しく解説しました。自筆証書遺言を作成した際には、ぜひ法務局の保管制度を利用し、安心して遺言を残すことを検討してみてください。