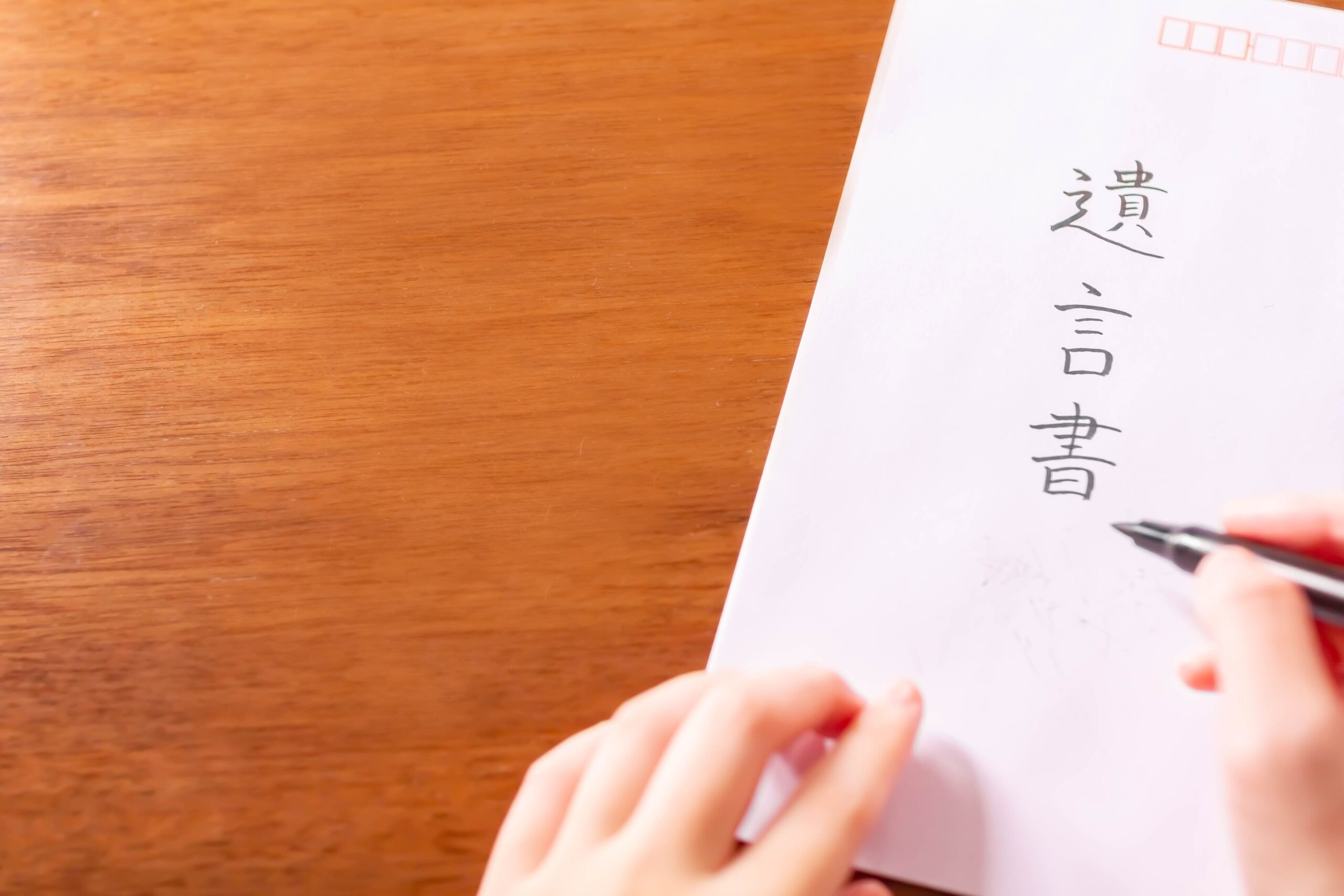自筆証書遺言とは?作成するメリットや作成時のポイントを解説
自筆証書遺言は費用を抑えて手軽に作成できる一方、形式不備や紛失リスクを抱えます。近年は法務局保管制度も始まり、安全性を高める選択肢が増えました。
本記事では、自筆証書遺言の定義と公正証書遺言との違い、作成メリット・デメリット、保管制度活用法、記載例と作成手順を網羅し、確実に遺志を残すポイントを詳しく解説します。
自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆し押印して成立する、民法上最も簡便な遺言方式です。公証人や証人を要さず、紙とペンさえあれば費用ゼロで即日作成・改訂できるため、プライバシーを保ちつつ自身の意思を柔軟に反映できます。
もっとも、形式要件を一つでも欠くと民法九六八条違反で無効となり、さらに紛失・改ざん・偽造の危険や、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける煩雑さがあります。
こうした弱点を補完する方法として、法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、窓口で形式審査を経たうえで原本が厳重保管され、検認が不要となるため、相続手続きが著しく円滑化します。
作成時には、財産目録が印字添付でも可となった改正点を踏まえ、誤記訂正や定期的な見直しを徹底し、保管制度や耐火金庫の併用で安全性を高めることが重要です。
また、署名押印は実印が望ましく、追記・訂正には二重線と訂正印、欄外注記を要するなど細部のルールも多いため、作成後に専門家チェックを受けると安心です。
自筆証書遺言と公正証書遺言との違い
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも遺言の一種ですが、その作成方法や法的効力においていくつかの重要な違いがあります。
まず、自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成するもので、特別な手続きは必要ありません。これに対して、公正証書遺言は、公証人が関与し、遺言者の意思を確認した上で作成されるため、より正式な手続きが求められます。
次に、法的効力の面では、自筆証書遺言は形式不備があると無効になるリスクがありますが、公正証書遺言は公証人が関与するため、形式的な要件が満たされている限り、無効になる可能性は低くなります。
また、公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や盗難のリスクも少なく、遺言の内容が確実に守られるという利点があります。さらに、費用面でも違いがあります。自筆証書遺言は基本的に費用がかからないのに対し、公正証書遺言は公証人に支払う手数料が必要です。
このように、遺言の種類によってそれぞれの特徴やメリット・デメリットが異なるため、自分の状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
自筆証書遺言を作成するメリット

自筆証書遺言には、いくつかの大きなメリットがあります。これから解説するメリットを考慮すると、自筆証書遺言は多くの人にとって有効な選択肢となるでしょう。
費用がほとんどかからない
自筆証書遺言の最大の魅力の一つは、その作成にかかる費用がほとんどかからない点です。公正証書遺言と比較すると、専門家に依頼する必要がないため、手数料や報酬が発生しません。
自分自身で遺言書を作成することができるため、必要なのは紙とペンだけで済むのです。このため、経済的な負担を抑えたい方にとって、自筆証書遺言は非常に有効な選択肢となります。
また、遺言書を作成する際に必要な書類や手続きもシンプルで、特別な知識やスキルがなくても取り組むことができます。これにより、相続に関する意思を明確にするためのハードルが低くなり、より多くの人々が自分の遺志を残すことが可能になります。
さらに、法務局の保管制度を利用することで、遺言書の紛失や盗難のリスクを軽減することもできます。この制度を活用することで、安心して自筆証書遺言を作成し、将来の相続に備えることができるのです。
手軽に作成する
自筆証書遺言の最大の魅力の一つは、その手軽さです。特別な手続きや専門家の助けを借りることなく、自分の手で遺言を作成できるため、時間や場所を選ばずに行えるのが大きな利点です。
必要なのは、紙とペンだけ。自分の思いをそのまま書き留めることができるため、感情や意志を直接伝えることができるのも特徴です。
また、作成にあたっての費用もほとんどかからないため、経済的な負担を気にすることなく、自分の遺志を残すことができます。公正証書遺言と異なり、役所や公証人に依頼する必要がないため、手続きが簡素化され、すぐにでも始められるのが魅力です。
このように、自筆証書遺言は非常に手軽に作成できるため、多くの人々にとって身近な選択肢となっています。自分の意志をしっかりと残したいと考える方にとって、まずはこの方法を検討することをお勧めします。
他社に遺言の内容知られない
自筆証書遺言の大きなメリットの一つは、遺言の内容を他者に知られずに作成できる点です。公正証書遺言の場合、遺言の内容は公証人によって記録され、必要に応じて第三者がその内容を確認できるため、プライバシーが保たれにくいという側面があります。
一方、自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成するため、内容を他人に知られることなく、秘密裏に遺志を表明することが可能です。
このプライバシーの保護は、特に相続に関する複雑な事情がある場合や、遺言の内容が家族間でのトラブルを引き起こす可能性がある場合に重要です。遺言者が自分の意志をしっかりと反映させるためには、他者に知られない環境で作成することが望ましいと言えるでしょう。
ただし、遺言の内容が秘密であることは、遺言の執行時に問題を引き起こす可能性もあります。遺言者が亡くなった後、遺言が存在することを知らない相続人がいる場合、遺言の執行が遅れることも考えられます。
自筆証書遺言を作成するデメリット

自筆証書遺言にはいくつかのデメリットがあります。メリットだけを見るのではなく、これから解説するデメリットを踏まえて自筆証書遺言を作成しましょう。
盗難や紛失のリスクがある
自筆証書遺言を作成する際の大きなデメリットの一つは、盗難や紛失のリスクです。自筆証書遺言は、基本的に自分で書いた文書であるため、保管場所や管理方法に注意を払わなければなりません。
例えば、家庭内での保管が不十分であったり、他人に見られる可能性がある場所に置いておくと、意図しない形で遺言が失われたり、悪用されたりする恐れがあります。
また、遺言書が紛失した場合、遺志を伝える手段が失われるだけでなく、相続人間でのトラブルを引き起こす原因にもなります。特に、遺言書が見つからなかった場合、法定相続に基づいて財産が分配されることになり、故人の意向が反映されない結果となることもあります。
このようなリスクを軽減するためには、遺言書を信頼できる場所に保管することが重要です。最近では、法務局に遺言書を保管する制度も整備されており、これを利用することで盗難や紛失のリスクを大幅に減少させることができます。
遺言の執行までに時間がかかる
自筆証書遺言のデメリットの一つとして、遺言の執行までに時間がかかる点が挙げられます。遺言が発見された後、相続手続きが始まるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。
まず、遺言の内容が法的に有効であるかどうかを確認するために、遺言書の検認が行われます。この審認手続きは、家庭裁判所で行われ、遺言の形式や内容に不備がないかをチェックします。
また、遺言の執行者が指定されている場合、その執行者が遺言の内容に基づいて相続手続きを進めることになりますが、執行者が遺言の内容を理解し、適切に手続きを行うためには、時間がかかることもあります。
特に、相続財産が多岐にわたる場合や、相続人間での合意が得られない場合には、手続きが長引くことがあります。
さらに、遺言の内容に対して異議が唱えられた場合、法的な争いが生じることもあり、その場合は裁判に発展することもあります。このような状況では、遺言の執行がさらに遅れる可能性があります。
不備がある場合法的に無効になるリスクがある
自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方で、形式的な不備があると法的に無効とされるリスクがあります。
例えば、遺言書の署名や日付が欠けている場合、または遺言の内容が不明瞭であると、遺言としての効力を失う可能性があります。このため、遺言を作成する際には、法律で定められた要件をしっかりと理解し、遵守することが重要です。
また、遺言書の内容が他の法律文書と矛盾している場合も、遺言の効力が問われることがあります。特に、相続に関する法律は複雑であり、誤解や誤記が生じやすいポイントです。したがって、遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
さらに、自筆証書遺言は、他の相続人とのトラブルを避けるためにも、明確で具体的な内容が求められます。
遺言の内容が不明瞭であったり、解釈の余地がある場合、相続人間での争いが生じることもあります。これらのリスクを回避するためには、慎重に内容を検討し、必要に応じて修正を加えることが大切です。
自筆証書遺言を書く際の6つのポイント

自筆証書遺言を作成する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。これから解説するポイントを押さえることで、より確実な遺志の表現が可能になります。
財産に関する資料や書類を集める
自筆証書遺言を作成する際には、まず自分の財産に関する資料や書類をしっかりと集めることが重要です。遺言書には、相続させたい財産の詳細を明確に記載する必要があります。
そのため、所有している不動産や預貯金、株式、貴金属などの資産を把握し、それに関連する書類を整理しておくことが求められます。
具体的には、不動産の登記簿謄本や評価証明書、預貯金の通帳や残高証明書、株式の取引明細書などが必要です。また、これらの書類は遺言書の内容を裏付ける重要な証拠となるため、正確な情報を記載するためにも、最新の情報を確認しておくことが大切です。
さらに、財産の種類によっては、特別な手続きや証明書が必要になる場合もあります。例えば、特定の財産に対する権利や負債がある場合、それらも考慮に入れた上で遺言書を作成する必要があります。
このように、財産に関する資料や書類を集めることは、自筆証書遺言を作成する上での第一歩であり、遺志を確実に伝えるための基盤となります。
遺言書のサイズは特に指定がない
自筆証書遺言を作成する際、遺言書のサイズについて特に法律での指定はありません。つまり、A4サイズの用紙でも、ハガキサイズの用紙でも、自由に選ぶことができます。
この柔軟性は、遺言書を作成する際の大きな利点の一つです。自分の書きやすいサイズや、保管しやすいサイズを選ぶことで、作成のハードルを下げることができます。
ただし、サイズに関して注意が必要なのは、遺言書があまりにも小さすぎる場合、内容が読みづらくなったり、記載が不十分になったりする可能性がある点です。特に、遺言書の内容が他の人に理解されやすいようにするためには、適切なサイズを選ぶことが重要です。
また、遺言書を保管する際にも、サイズが影響を与えることがあります。例えば、保管場所に合わせたサイズを選ぶことで、紛失や損傷のリスクを減らすことができます。
相続内容を明らかにする
自筆証書遺言を作成する際には、相続内容を明確に記載することが非常に重要です。相続内容とは、遺産の分配方法や相続人の指定を指します。
具体的には、どの財産を誰に相続させるのか、または特定の財産を誰に譲るのかを明記する必要があります。これにより、遺言の内容が明確になり、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、不動産や預貯金、株式などの具体的な財産名やその評価額を記載することが望ましいです。また、相続人の名前や続柄も正確に記載することで、後々の混乱を避けることができます。さらに、特定の条件を付ける場合も、その内容を具体的に記載することが重要です。
相続内容を明らかにすることで、遺言の執行者が遺志を正確に実行できるようになります。これにより、遺族が遺言の内容を理解しやすくなり、相続手続きがスムーズに進むことが期待できます。
財産目録のみ代筆もしくは、パソコンでの作成が可能である
自筆証書遺言を作成する際、特に財産目録については柔軟な対応が可能です。遺言書全体を自筆で書く必要がある一方で、財産目録に関しては代筆やパソコンでの作成が認められています。
これにより、手書きが難しい方や、パソコンを使い慣れている方でも、正確かつ見やすい形で財産を整理することができます。財産目録は、遺言の重要な部分であり、相続人がどのような財産を受け取るのかを明確に示す役割を果たします。
したがって、財産目録を作成する際には、所有する不動産や預貯金、株式などの詳細を正確に記載することが求められます。代筆やパソコンでの作成を利用することで、誤記や漏れを防ぎ、より信頼性の高い遺言書を作成することが可能です。
ただし、財産目録を代筆またはパソコンで作成する場合でも、遺言書全体の署名や日付は自筆で行う必要があります。
遺言執行者の指定を検討する
自筆証書遺言を作成する際には、遺言執行者の指定を検討することが重要です。遺言執行者とは、遺言の内容を実行する責任を持つ人物のことを指します。遺言執行者がいることで、遺言の内容が確実に実行されることが期待でき、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
遺言執行者には、信頼できる親族や友人を選ぶことが一般的ですが、専門家である弁護士や司法書士を指定することも可能です。特に、相続財産が多岐にわたる場合や、相続人間に対立が予想される場合には、専門家を選ぶことで、よりスムーズに遺言の執行が行われるでしょう。
遺言執行者を指定する際には、その人物に対して事前に相談し、承諾を得ることが大切です。無理に指定した場合、執行者がその役割を果たさない可能性もあるため、信頼関係を築くことが重要です。
また、遺言書には執行者の氏名や連絡先を明記し、必要に応じてその理由も記載しておくと良いでしょう。このように、遺言執行者の指定は、自筆証書遺言を作成する上で欠かせない要素です。
共同の遺言は無効となる
自筆証書遺言を作成する際には、共同の遺言が無効であることを理解しておくことが重要です。日本の法律では、遺言は原則として個人が単独で作成するものであり、複数の人が共同で作成した遺言は法的に認められません。
このため、もし夫婦や親子などが共同で遺言を作成した場合、その遺言は無効となり、遺志が正しく反映されない可能性があります。
共同の遺言が無効となる理由は、遺言の内容が各相続人の意向を正確に反映することが難しいためです。遺言は個人の意思を明確に示すものであり、他者との合意や妥協が入ることで、その意図が曖昧になってしまうからです。
この点を踏まえ、遺言を作成する際には、自分の意思をしっかりと表現することが大切です。もし共同での遺言作成を希望する場合は、各自が別々に自筆証書遺言を作成し、それぞれの意向を明確に示すことが推奨されます。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方で、いくつかのリスクや注意点も存在します。費用を抑えられることや、他者に内容を知られずに遺志を残せる点は大きなメリットですが、盗難や紛失のリスク、形式不備による無効の可能性も考慮しなければなりません。
本記事では、自筆証書遺言の基本的な理解を深めるために、その定義や公正証書遺言との違い、作成のメリット・デメリット、さらには具体的な作成手順やポイントについて詳しく解説しました。
遺言を作成する際は、これらの情報を参考にし、自分の遺志を確実に残すための準備を進めていくことが重要です。自筆証書遺言を通じて、あなたの大切な思いを次世代にしっかりと伝えていきましょう。