被相続人とは?相続割合や相続順位の考え方を解説!
被相続人とは死亡によって財産や負債を承継される立場の人を指しますが、相続順位や法定相続分を誤解すると遺産分割や納税で思わぬトラブルに発展します。
本記事では、被相続人の定義と相続順位、法定相続割合の考え方を図解し、遺言書や生前贈与、家族信託などで希望を反映させる方法までわかりやすく解説します。
被相続人とは
被相続人とは、死亡によりその権利義務が包括的に相続人へ移転する起点となる人を指します。民法896条は「相続は被相続人の死亡によって開始し、相続人は一切の権利義務を承継する」と規定し、借金や連帯保証債務などマイナス資産も相続対象に含めています。
遺言があれば原則として意思が優先されますが、方式違反や遺留分(1042条)を侵害する内容は減殺や無効の対象となります。
遺言が無い場合は法定相続人と法定相続分が適用され、相続人は死亡を知った日から3か月以内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択しなくてはなりません。
誤った選択をすると負債も無制限に承継する恐れがあるため、戸籍や財産目録を速やかに調査し専門家へ相談することが安全策です。
近年は、デジタル資産やSNSアカウントも承継対象となるため、生前にエンディングノートや遺言書保管制度を活用し、資産所在とパスワードを整理しておくと相続人の負担と紛争リスクを大きく減らせます。
相続人になる時の相続順位の考え方とは
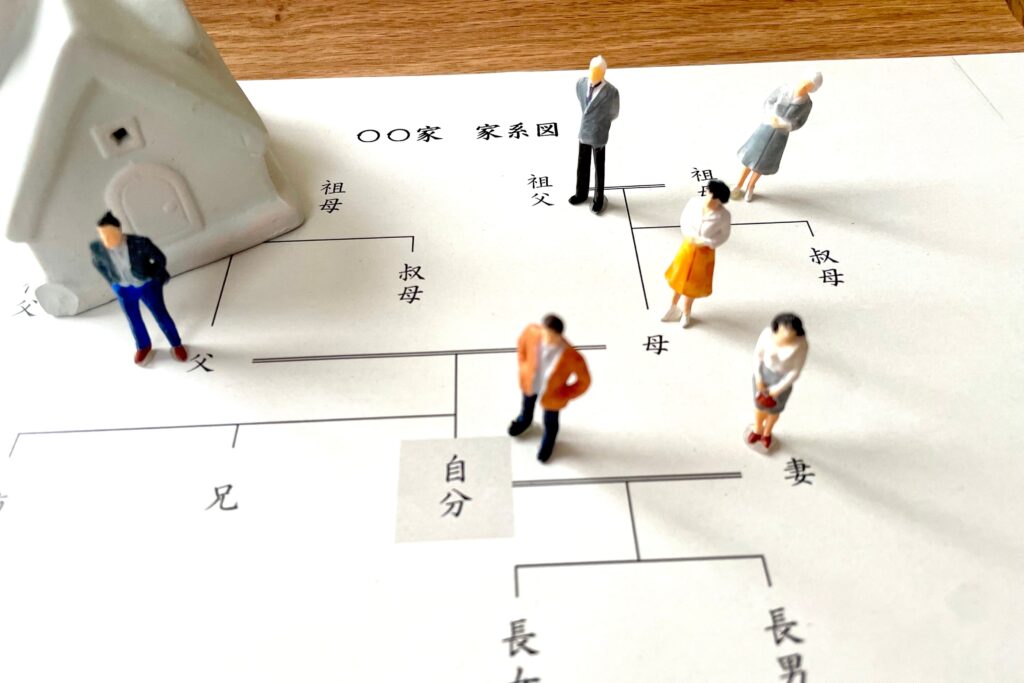
相続人の順位は、被相続人が亡くなった際に誰がどのように財産を受け継ぐかを決定する重要な要素です。相続順位は法律で定められており、一般的には子供、親、兄弟姉妹の順に相続権が認められています。
第1順位:子供
相続において、被相続人の子供は最も重要な存在であり、相続順位の第1順位に位置づけられています。これは、法律に基づくものであり、被相続人が亡くなった際に、子供たちがその財産を受け継ぐ権利を持つことを意味します。
子供が複数いる場合、相続分は均等に分配されるのが基本です。たとえば、被相続人に子供が2人いる場合、遺産は2等分され、それぞれが半分ずつ受け取ることになります。
また、子供がすでに亡くなっている場合、その子供の子供、つまり被相続人の孫が代襲相続することができます。これにより、相続の権利が次世代に引き継がれる仕組みが整っています。
このように、子供は相続において非常に重要な役割を果たしており、相続手続きの際にはその存在をしっかりと考慮する必要があります。相続に関するトラブルを避けるためにも、事前に相続についての理解を深めておくことが大切です。
第2順位:親
相続において、被相続人の親は第2順位の相続人として位置づけられています。これは、被相続人に子供がいない場合に適用されるルールです。
親が相続人となる場合、法定相続分は被相続人の財産の半分を占めることになります。つまり、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が1/2、親が1/2を相続することになります。
親が相続人となるケースは、特に被相続人が独身であったり、子供がいない場合に多く見られます。この場合、親は被相続人の財産を受け取る権利を持ちますが、もし親がすでに亡くなっている場合は、親の兄弟姉妹(つまり被相続人の叔父や叔母)が相続人となります。
また、親が相続人となる場合、相続の手続きにおいて注意が必要です。特に、親が高齢である場合、相続手続きが複雑になることがあります。相続税の申告や遺産分割協議など、専門的な知識が求められる場面も多いため、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
第3順位:兄弟姉妹
相続における兄弟姉妹の位置づけは、被相続人が亡くなった際に重要な役割を果たします。相続順位の第3順位に位置する兄弟姉妹は、被相続人に直系の子供や親がいない場合に相続権を持つことになります。つまり、被相続人に子供や親がいない場合、兄弟姉妹が遺産を受け取る権利を持つのです。
兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は被相続人の財産を兄弟姉妹の人数で均等に分けることになります。例えば、被相続人に兄弟姉妹が3人いる場合、遺産は3等分され、それぞれが同じ割合で相続することになります。
ただし、兄弟姉妹の中に先に亡くなった者がいる場合、その子供が代襲相続することもあります。この場合、亡くなった兄弟姉妹の子供が、親の代わりに相続権を持つことになります。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続に関するトラブルが発生することも少なくありません。特に、遺産の分割方法や評価額について意見が分かれることが多いため、事前に話し合いを行うことが重要です。
被相続人の相続の割合とは

被相続人の相続の割合は、相続人の構成や関係性によって異なります。相続人が誰であるかを明確に理解することが、遺産分割の際のトラブルを避けるために重要です。次のセクションでは、具体的なケースごとに相続の割合について詳しく解説していきます。
配偶者以外に法定相続人がいない場合
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は法定相続人として優先的に相続権を持ちます。しかし、配偶者以外に法定相続人がいない場合、相続は配偶者に全て譲られることになります。この状況では、配偶者は被相続人の財産を単独で相続することができ、他の親族からの相続権は発生しません。
具体的には、配偶者が相続する財産には、現金や不動産、預貯金、株式などが含まれます。これにより、配偶者は被相続人の遺産を自由に管理し、利用することが可能です。ただし、相続税の負担も配偶者が負うことになるため、相続税の計算や納付についても注意が必要です。
また、配偶者が相続する際には、遺言書が存在する場合、その内容に従って相続が行われることになります。
遺言書がない場合は、法律に基づいて相続が進められますが、配偶者が唯一の法定相続人であれば、特に問題は生じません。このように、配偶者以外に法定相続人がいない場合は、相続手続きが比較的スムーズに進むことが多いと言えるでしょう。
被相続人の親がいる場合
被相続人に親がいる場合、相続の割合は法定相続分に基づいて決まります。日本の民法では、相続人の順位が定められており、被相続人の親は第2順位の相続人として位置づけられています。つまり、被相続人に配偶者や子供がいない場合、親が相続人として遺産を受け取る権利を持つことになります。
具体的には、被相続人の親が1人の場合、その親が全ての遺産を相続します。しかし、被相続人に複数の親がいる場合、例えば養親と実親がいる場合には、相続権がどのように分配されるかが問題となります。
また、被相続人の親が亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。この場合、兄弟姉妹は第3順位の相続人として、親の代わりに相続権を持つことになります。相続の割合は、兄弟姉妹の数に応じて均等に分配されることが基本です。
このように、被相続人の親がいる場合の相続は、法定相続分に基づいて明確に定められていますが、実際の相続手続きでは、遺言書の有無や他の相続人の存在によっても影響を受けるため、注意が必要です。
被相続人の兄弟姉妹がいる場合
被相続人に兄弟姉妹がいる場合、相続の割合は法定相続分に基づいて決まります。まず、被相続人の配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、残りの財産は兄弟姉妹と配偶者の間で分配されます。具体的には、配偶者が相続する割合は法定相続分の半分となり、残りの半分が兄弟姉妹に分配されます。
兄弟姉妹が複数いる場合、残された財産はその人数で均等に分けられます。たとえば、被相続人に配偶者と2人の兄弟姉妹がいる場合、配偶者が相続するのは全体の50%、残りの50%は2人の兄弟姉妹で分け合うことになります。この場合、各兄弟姉妹は25%ずつ相続することになります。
一方、被相続人に配偶者がいない場合、兄弟姉妹は法定相続人として全財産を均等に相続します。つまり、兄弟姉妹が3人いる場合、各自が33.3%ずつ相続することになります。
このように、兄弟姉妹がいる場合の相続割合は、配偶者の有無や兄弟姉妹の人数によって大きく変わるため、注意が必要です。相続に関するトラブルを避けるためには、事前に相続のルールを理解し、必要に応じて遺言書を作成することが重要です。
被相続人の甥や姪がいる場合
被相続人に甥や姪がいる場合、相続の取り扱いは少し複雑になります。一般的に、甥や姪は法定相続人には含まれません。法定相続人は、配偶者、子供、親、兄弟姉妹といった直系の親族に限られます。しかし、甥や姪が相続に関与するケースも存在します。
まず、甥や姪が相続人となるのは、被相続人に直系の相続人がいない場合です。この場合、兄弟姉妹が亡くなっていると、甥や姪がその代わりに相続権を持つことになります。
具体的には、被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供である甥や姪が相続人として登場します。
相続分は、亡くなった兄弟姉妹の子供たちで均等に分けられます。たとえば、被相続人の兄弟姉妹が2人いて、それぞれに子供がいる場合、被相続人の財産はその兄弟姉妹の子供たちに均等に分配されることになります。
また、被相続人が遺言書を残している場合、甥や姪に特定の財産を譲ることも可能です。この場合、遺言書の内容が優先されるため、法定相続分とは異なる分配が行われることになります。
遺言書で配偶者に全て譲ると書かれていた場合
被相続人が遺言書において配偶者に全ての財産を譲ると明記していた場合、その内容は法的に有効とされます。
遺言書は、被相続人の最終的な意思を示す重要な文書であり、相続におけるトラブルを避けるための有力な手段です。特に、配偶者に全てを譲るという明確な指示がある場合、他の相続人はその意向を尊重する必要があります。
ただし、遺言書があっても、法定相続分に基づく権利は残ります。例えば、被相続人に子供がいる場合、配偶者は法定相続分を超えて全ての財産を受け取ることができるとは限りません。
遺言書の内容が法定相続分に反する場合、他の相続人は遺留分を主張する権利があります。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる財産の割合であり、これにより相続人間の公平性が保たれています。
したがって、遺言書で配偶者に全て譲ると記載されている場合でも、他の相続人との関係や遺留分について十分に理解しておくことが重要です。
被相続人の希望を相続に反映させる方法とは

被相続人が望む形で相続を行うためには、いくつかの方法があります。これから解説する方法を駆使することで、被相続人の希望をしっかりと反映させることができるでしょう。
遺言書に反映させる
遺言書は、被相続人が自らの意思を明確に示すための重要な手段です。相続に関するトラブルを避けるためには、遺言書を作成することが非常に有効です。
遺言書には、財産の分配方法や特定の相続人に対する希望を具体的に記載することができます。これにより、相続人間での誤解や対立を防ぎ、スムーズな遺産分割を実現することが可能になります。
遺言書にはいくつかの形式がありますが、一般的には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類が存在します。自筆証書遺言は、被相続人が自ら手書きで作成するもので、比較的簡単に作成できますが、法的要件を満たさないと無効になる可能性があります。
一方、公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、法的な信頼性が高く、相続人にとっても安心です。
遺言書を作成する際には、相続人の名前や相続割合、特定の財産の譲渡先などを明確に記載することが重要です。また、遺言書の内容は、被相続人の意思を反映させるために、定期的に見直すことも推奨されます。
生前贈与を活用する
生前贈与は、被相続人が生存中に自らの財産を特定の相続人や他の人に贈与する手段です。この方法を利用することで、相続時のトラブルを未然に防ぎ、希望する相続分を実現することが可能になります。生前贈与の最大の利点は、贈与を受けた人がその財産を早期に利用できる点です。
生前贈与には、贈与税がかかる場合がありますが、年間110万円までの贈与については非課税となるため、計画的に贈与を行うことで税負担を軽減することができます。
また、贈与を行う際には、贈与契約書を作成することが重要です。これにより、贈与の事実を明確にし、後のトラブルを避けることができます。
さらに、生前贈与は相続財産の圧縮にも寄与します。相続財産が減少することで、相続税の負担が軽くなる可能性があります。特に高額な不動産や金融資産を持つ場合、早めに生前贈与を行うことで、相続時の評価額を下げることができるため、計画的な資産管理が求められます。
家族信託を利用する
家族信託は、被相続人が自分の財産を生前に管理し、相続時にスムーズに承継できるようにするための有効な手段です。
信託契約を結ぶことで、被相続人は自分の財産を信頼できる家族に託し、特定の条件に基づいてその財産を管理・運用してもらうことができます。この方法は、相続人間のトラブルを未然に防ぐだけでなく、相続税対策にも役立ちます。
家族信託の最大の利点は、被相続人が生前に財産の使い道や分配方法を明確に指定できる点です。例えば、特定の相続人に特定の財産を譲ることや、相続人が未成年の場合にその財産を管理する方法を決めることができます。
さらに、家族信託は、相続が発生した際に遺産分割協議を行う必要がなくなるため、手続きが簡素化されます。これにより、相続人同士の対立を避け、円満な相続を実現することができます。
ただし、家族信託を利用する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。信託契約の内容や運用方法について十分に理解し、適切な手続きを行うことで、より安心して相続を迎えることができるでしょう。
相続廃除を活用する
相続廃除とは、被相続人が特定の相続人に対して相続権を剥奪する手続きを指します。この制度は、被相続人が生前に相続人に対して重大な不正行為や不適切な行動を行った場合に利用されることが一般的です。
例えば、相続人が被相続人に対して虐待を行ったり、相続人としての義務を果たさなかった場合などが該当します。相続廃除を行うためには、被相続人が遺言書にその旨を明記する必要があります。遺言書には、相続廃除の理由を具体的に記載することが求められます。
この手続きは、相続人の権利を制限するため、法的な手続きが必要となるため、専門家の助言を受けることが推奨されます。
また、相続廃除は一度行われると、原則として取り消すことはできません。そのため、被相続人は慎重に判断し、相続廃除を行うかどうかを決定する必要があります。
相続廃除を活用することで、被相続人の意向を反映させ、遺産分割におけるトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
まとめ
被相続人について理解することは、相続に関するトラブルを避けるために非常に重要です。被相続人とは、亡くなった方のことを指し、その財産や負債は相続人に引き継がれます。
相続順位や法定相続分を正しく理解することで、遺産分割や納税における誤解を防ぎ、スムーズな相続手続きを実現できます。
相続順位は、子供、親、兄弟姉妹といった順に決まっており、それぞれの順位に応じた相続割合が存在します。また、遺言書や生前贈与、家族信託などを活用することで、被相続人の希望を相続に反映させることも可能です。
本記事を通じて、被相続人の定義や相続順位、法定相続割合の考え方を理解し、相続に関する知識を深めていただけたら幸いです。相続は人生の一大事であり、事前にしっかりと準備をすることで、家族の絆を守ることができるでしょう。



