内縁の妻は預金引き出しできる?死亡後の遺産相続・財産・遺品整理
内縁関係は、婚姻届を提出していない事実婚の状態を指し、法律上の夫婦とは異なるため、パートナーが亡くなった際の遺産相続や財産に関する権利に大きな違いが生じます。
特に、預金引き出しや遺品整理の場面では、法律婚の配偶者と同様には扱われないため、注意が必要です。
内縁の妻は、原則として亡くなった夫の預金を引き出すことができず、相続権もありません。そのため、残されたパートナーが財産を受け取るためには、生前からの対策が非常に重要となります。
【結論】内縁の妻は原則として夫の預金を引き出せません
内縁の妻は、夫の預金を原則として引き出すことができません。
夫が亡くなると、銀行は口座名義人の死亡を知った時点でその銀行口座を凍結するため、たとえ内縁の妻が夫の通帳やキャッシュカードを持っていたとしても、引き出しは不可能になります。
銀行は、正当な権利者である法定相続人以外には預金の払い戻しを行わないため、内縁の妻は法律上の配偶者ではないため、預金へのアクセスが制限されるのです。
葬儀費用や当面の生活費に充てるため、故人の預金を引き出したいと考える場合でも、法定相続人の同意がなければ、原則として引き出しは認められません。
内縁の妻に相続権がない理由|法律婚との法的な違い
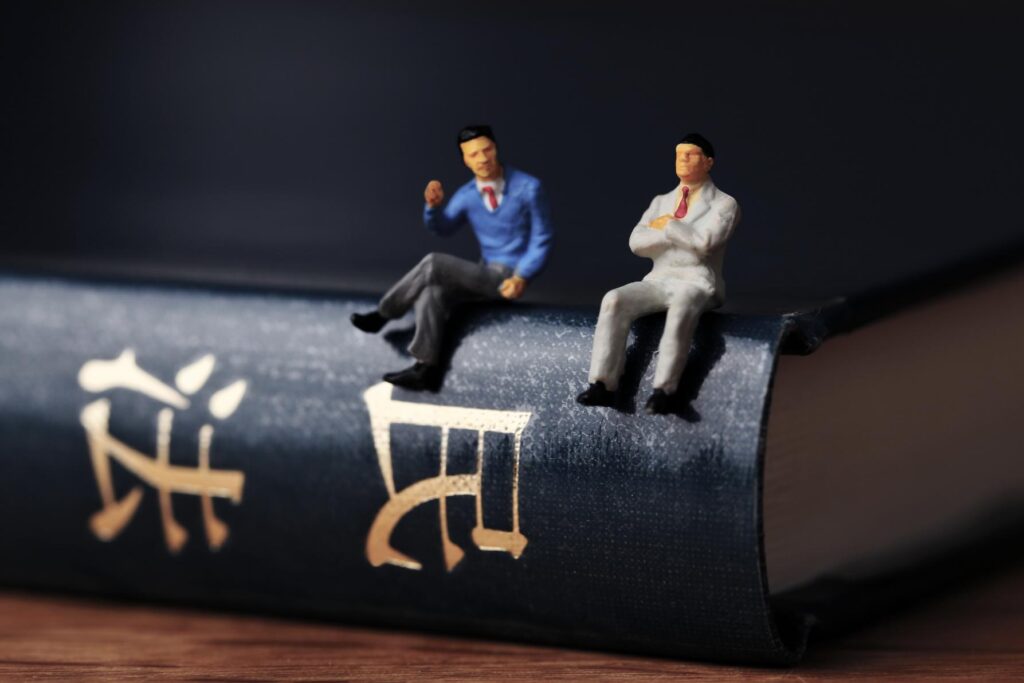
内縁の妻が夫の相続人になれないのは、日本の法律が定める相続制度において、法定相続人の範囲に「戸籍上の配偶者」のみを認めているためです。
内縁関係は、婚姻届を提出していない事実婚の状態であり、法律上の夫婦とは異なる法的な位置づけにあります。
この点が、法律婚の配偶者との決定的な違いとなります。
法律婚であれば、配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻は戸籍上の関係がないため、相続権が認められません。
法的に「内縁関係」と認められるための3つの要件
法的に内縁関係と認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
第一に、当事者双方に婚姻の意思があること、つまり事実上夫婦として共同生活を営む合意があることです。
第二に、共同生活の実態があること、具体的には同居して家計を共にしている状態が一定期間継続していることなどが挙げられます。
一般的に、3年以上の同居期間があれば、婚姻意思があると推定されることが多いようです。
第三に、社会的に夫婦として認識されていること、例えば周囲の家族や知人から夫婦として扱われていることや、住民票に「未届の妻(夫)」と記載されているなどの客観的事実がこれに当たります。
これらの要件がすべて満たされている必要はありませんが、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。
法定相続人になれないことが法律婚との決定的な違い
法律婚の配偶者は、民法によって常に法定相続人として認められ、被相続人の財産を相続する権利を有します。
しかし、内縁の妻は、どれほど長年連れ添い、夫婦同然の生活を送っていたとしても、法律上の配偶者ではないため、夫の財産に対する相続権がありません。
これが法律婚との決定的な違いであり、内縁関係における財産承継の大きな課題となります。
内縁の妻は、寄与分や特別寄与料の請求も認められないため、夫の財産形成に貢献していたとしても、その貢献が直接的に相続財産として評価されることはありません。
夫の死後に預金を引き出せないことで起こる具体的な問題
夫が亡くなった後、内縁の妻が夫の預金を引き出せないことによって、様々な問題が生じる可能性があります。
特に、夫の銀行口座が凍結されると、葬儀費用や当面の生活費の支払いに困窮するケースも少なくありません。
故人の財産をめぐって、法定相続人との間でトラブルが発生することもあります。
金融機関が死亡を知ると故人の預金口座は凍結される
金融機関は、口座名義人の死亡を知ると、遺産を巡るトラブルを防ぐ目的で、原則としてその預金口座を凍結します。これにより、故人の銀行口座からの引き出しや送金が一切できなくなります。たとえ内縁の妻が夫のキャッシュカードや通帳を所持していても、口座が凍結されてしまえば、預金を引き出すことは不可能となります。この凍結を解除し、預金を引き出すためには、原則として法定相続人全員の同意と、所定の手続きが必要となるため、内縁の妻が単独で預金にアクセスすることは極めて困難です。
葬儀費用や当面の生活費の支払いに困る可能性がある
夫が亡くなると、葬儀費用や今後の生活費など、緊急に現金が必要となる場面が多々あります。
しかし、内縁の妻は夫の預金口座から自由に預金を引き出すことができないため、これらの費用の支払いに困る可能性があります。
特に、夫の預金が主な収入源であった場合や、手元に十分な現金がない場合には、生活が立ち行かなくなる事態も考えられます。
葬儀費用は高額になることもあり、法定相続人の協力が得られない場合、大きな負担となるでしょう。
故人の財産をめぐり法定相続人とトラブルになるケースも
内縁の夫が亡くなった際、内縁の妻に相続権がないため、故人の財産は法定相続人(子や親、兄弟姉妹など)に引き継がれます。
内縁の妻が夫の財産にアクセスしようとすると、法定相続人との間でトラブルに発展するケースが少なくありません。
特に、生前に夫が内縁の妻に財産を残したいという意思を明確にしていなかった場合や、法定相続人との関係性が希薄な場合には、遺産分割をめぐって紛争が生じる可能性が高まります。
感情的な対立が生じることもあり、円満な解決が困難になる場合もあります。
内縁の妻が財産を受け取るための3つの生前対策
内縁の妻に夫の財産を確実に残すためには、夫が生きている間に適切な生前対策を講じることが不可欠です。
何も対策をしないままでは、内縁の妻が夫の死亡後に財産を受け取ることは困難になります。
ここでは、内縁の妻が財産を受け取るための主な3つの生前対策について解説します。
対策1:遺言書を作成してもらい財産を遺贈する
夫に遺言書を作成してもらい、内縁の妻へ財産を「遺贈」してもらう方法は、内縁の妻が財産を受け取るための最も確実な方法の一つです。
遺言書は、被相続人の生前の意思を強く反映するものであり、法定相続よりも優先されるため、法律上の婚姻関係がなくても財産を譲り渡すことが可能になります。
遺言書には、現金・預金・不動産・株式など、遺贈する財産の種類に制限はありません。
ただし、遺言書の内容が法定相続人の遺留分(最低限保証された相続分)を侵害しないように配慮が必要です。
トラブルを避けるためにも、公正証書遺言の作成を検討し、専門家に相談することをおすすめします。
対策2:生前に財産を贈与してもらう手続きを進める
夫が生きているうちに、内縁の妻に財産を生前贈与してもらう方法も有効な対策です。生前贈与であれば、婚姻関係等がなくても当事者間の合意によって自由に財産を譲り渡すことができます。
贈与契約は口頭でも成立しますが、後々のトラブルを防ぐためにも、贈与契約書を作成し、贈与の意思を明確にしておくことが重要です。
ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。計画的に贈与を進めることで、税負担を抑えながら財産を移転することが可能ですが、一度に高額な財産を贈与すると税率の高い贈与税が課されるため、注意が必要です。
対策3:生命保険の受取人に指定してもらう方法
夫を被保険者とし、内縁の妻を生命保険の受取人に指定する方法も、財産を渡す有効な手段です。
生命保険金は、受取人固有の財産とみなされ、相続財産とは区別されるため、遺産分割協議の対象にはなりません。
これにより、他の法定相続人の影響を受けずに、内縁の妻が直接保険金を受け取ることが可能になります。
ただし、保険会社によっては、内縁の妻を受取人に指定するために、戸籍上の配偶者がいないこと、一定期間の同居や生計同一関係が証明できることなどの条件を設けている場合があります。
事前に保険会社に確認し、必要な手続きを進めることが重要です。
夫の死後に内縁の妻ができる財産に関する手続き
夫が亡くなった後でも、内縁の妻ができる財産に関する手続きがいくつか存在します。
これらの手続きは、生前対策が行われていなかった場合や、特定の条件を満たす場合に、内縁の妻が一定の財産を受け取ったり、生活の保障を得たりするためのものです。
他に相続人がいない場合に家庭裁判所へ特別縁故者の申し立てを行う
もし亡くなった夫に法定相続人が一人もいない場合、内縁の妻は家庭裁判所へ「特別縁故者」の申し立てを行うことで、故人の財産の一部または全部を受け取れる可能性があります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など、被相続人と特別に親密な関係にあった者を指します。
内縁の妻は、この「生計を同じくしていた人」に該当すると判断されることがあります。
ただし、特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所での複雑な手続きと、厳格な審査基準を満たす必要があり、必ずしも財産が分与されるとは限りません。
条件を満たせば遺族年金を受け取れる可能性がある
内縁の妻は相続権がない一方で、一定の条件を満たせば遺族年金を受け取れる可能性があります。
遺族年金は、被保険者によって生計を維持されていた遺族の生活保障を目的とした制度であり、法律婚の配偶者に限らず、事実婚関係にある者も受給対象となる場合があります。
受給するためには、事実婚関係の証明や、生計維持関係にあったことの証明など、年金事務所に提出する多くの書類が必要となります。
これらの要件をクリアすることで、夫の死亡後の経済的な不安を軽減できることがあります。
公的な制度であるため、要件や手続きの詳細を年金事務所に確認することが重要です。
二人の協力で築いた共有財産の分与を請求する
内縁関係であっても、二人の協力によって築き上げた財産、いわゆる「共有財産」については、離婚時と同様に財産分与を請求する権利があります。
これは、夫婦共同生活を送る中で形成された財産は、実質的に二人の共有財産であるという考え方に基づくものです。
例えば、夫名義の預金であっても、内縁の妻が家計を管理し、共同で生活費を負担していたなど、内縁の妻の貢献が認められる場合には、その分に応じた財産分与を請求できる可能性があります。
ただし、何が共有財産に当たるのか、その貢献度をどのように評価するのかなど、具体的な分与額をめぐっては、法的な知識や交渉が必要となるため、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
預金以外に知っておきたい権利と税金の注意点
内縁の妻は、預金や相続財産以外にも、夫の死亡後に知っておくべき権利や、税金に関する注意点があります。
これらを把握しておくことで、将来の生活設計やトラブル回避に役立つでしょう。
夫名義の家に住み続けるための居住権について
夫名義の家に内縁の妻が住んでいた場合、夫の死亡後にその家に住み続けられるかが問題となります。
内縁の妻には相続権がないため、原則として夫名義の家を相続することはできません。
しかし、判例上、賃借権が認められるケースがあります。
これは、内縁の夫婦が共同でアパートなどを借りていたとみなされ、夫が亡くなってもすぐに賃借権がなくなるわけではないという考え方に基づきます。
ただし、全てのケースで認められるわけではないため、生前に夫に遺言書で居住権について明記してもらうか、賃貸借契約を内縁の妻名義に変更するなどの対策を講じることが望ましいでしょう。
内縁の妻が遺産を受け取ると相続税が2割加算される
内縁の妻が遺言書による遺贈や生前贈与などで夫の遺産を受け取った場合、相続税が課税される可能性があります。
特に注意すべきは、法律上の配偶者や一親等の血族以外の人が遺産を取得した場合、相続税額に2割が加算される「相続税の2割加算」が適用される点です。
内縁の妻は法律上の配偶者ではないため、この2割加算の対象となり、通常の相続人よりも税負担が重くなります。
また、法律上の配偶者であれば適用される「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などの税制優遇措置も利用できないため、さらに税額が高くなる可能性があります。
夫が認知した子供には相続権が認められる
内縁の夫と内縁の妻の間に生まれた子どもは、夫がその子どもを認知していれば、法律上の親子関係が成立し、嫡出子と同様に相続権が認められます。
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子どもについて、父親が自分の子どもであると認める手続きです。
認知された子どもは、父親の法定相続人となり、遺産を相続する権利を有します。
もし夫が子どもを認知していなかった場合、その子どもは法律上の「子」とはみなされず、相続権は発生しません。
そのため、内縁関係に子どもがいる場合は、生前の認知手続きが非常に重要となります。
まとめ
内縁の妻は法律上の配偶者ではないため、原則として夫の死亡後に預金を引き出す権利や、夫の財産を相続する権利はありません。
夫が亡くなると、銀行口座は凍結され、葬儀費用や当面の生活費の確保に困窮する可能性があり、さらに故人の財産をめぐって法定相続人との間でトラブルが生じることもあります。
しかし、生前の適切な対策を講じることで、内縁の妻に財産を確実に残すことは可能です。
具体的には、遺言書による遺贈、生前贈与、生命保険の受取人指定などが有効な手段となります。
また、夫の死後でも、他に法定相続人がいない場合の特別縁故者の申し立てや、一定の条件を満たせば遺族年金を受け取る権利、二人の協力で築いた共有財産の分与請求などが可能です。
内縁の妻が遺産を受け取る際には相続税の2割加算が適用されるなど、税金面での注意点も多く存在します。
夫名義の家に住み続けるための居住権や、夫が認知した子どもに相続権が認められる点なども含め、内縁関係における財産や権利に関する知識を深め、万が一の事態に備えることが重要です
これらの複雑な問題については、法律や相続に詳しい専門家への相談を強くおすすめします。



