みなし相続財産とは?種類や取得する場合の注意点を解説
みなし相続財産とは、法律上は相続や遺贈ではなくても被相続人の死亡を原因に取得するため相続税の課税対象となる財産を指します。代表例は生命保険金や死亡退職金、生前贈与の一定額などで、非課税枠の適用条件や受取人による税率加算に注意が必要です。
本記事では、みなし相続財産と通常の相続財産の違い、種類ごとの課税ルール、取得時に押さえるべき申告・節税のポイントを詳しく解説します。
みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことを原因として取得される財産のうち、法律上の相続や遺贈には該当しないものを指します。
具体的には、生命保険金や死亡退職金、生前贈与の一定額などが代表的な例です。これらの財産は、相続税の課税対象となるため、注意が必要です。
相続税は、相続財産の総額に基づいて計算されますが、みなし相続財産もその一部として扱われます。つまり、相続人が受け取る財産の中には、相続手続きとは無関係に取得するものが含まれているため、税務上の取り扱いを理解しておくことが重要です。
また、みなし相続財産には一定の非課税枠が設けられている場合もありますが、その適用条件は複雑です。受取人によっては、税率が加算されることもあるため、事前にしっかりと確認しておくことが求められます。
みなし相続財産と相続財産の違いとは
みなし相続財産と相続財産は、相続税の観点から見ると異なる性質を持つ財産です。まず、相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産で、相続や遺贈によって法定相続人が取得するものを指します。これには不動産、預貯金、株式などが含まれ、相続税はこれらの財産の総額に基づいて課税されます。
一方、みなし相続財産は、法律上の相続や遺贈によるものではないにもかかわらず、被相続人の死亡を原因として取得される財産です。具体的には、生命保険金や死亡退職金、生前贈与の一定額などが該当します。これらの財産は、相続税の課税対象となるため、注意が必要です。
このように、みなし相続財産は相続財産とは異なるルールで扱われるため、相続税の計算や申告において特別な配慮が求められます。
特に、みなし相続財産は相続放棄を行った場合でも受け取ることができるため、相続人がどのように財産を取得するかを理解しておくことが重要です。相続財産とみなし相続財産の違いを把握することで、適切な相続税対策を講じることが可能になります。
みなし相続財産の種類とは
みなし相続財産には、主に生命保険金、死亡退職金、生前に受けた贈与財産などが含まれます。これらは被相続人の死亡を契機に取得されるため、相続税の課税対象となります。
生命保険金
生命保険金は、被相続人が契約した生命保険の保険金であり、被相続人の死亡を契機に受取人に支払われるものです。この保険金は、相続税の課税対象となるみなし相続財産の一つとして位置づけられています。
具体的には、保険金の受取人が被相続人の配偶者や子供である場合、一定の非課税枠が適用されるため、相続税の負担を軽減することが可能です。
ただし、生命保険金の受取人が被相続人の親や兄弟、その他の親族である場合、相続税が課税されることになります。
また、受取人が複数いる場合は、保険金の分配に応じてそれぞれの受取人に課税されるため、注意が必要です。さらに、生命保険金は相続財産とは異なり、遺産分割の対象外となるため、相続人間での話し合いに影響を与えない点も重要です。
このように、生命保険金は相続税の観点から特有の取り扱いがあるため、受取人はその税務上の影響を十分に理解し、適切な手続きを行うことが求められます。
死亡退職金
死亡退職金とは、被相続人が勤務していた会社から支給される、死亡に伴う退職金のことを指します。この金額は、被相続人が在職中に積み立てた退職金制度に基づいて計算され、通常はその人の勤続年数や給与水準に応じて決定されます。
死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として受け取るものであり、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。
この死亡退職金は、受取人が指定されている場合、通常はその指定された受取人に直接支払われます。受取人が配偶者や子供であれば、相続税の非課税枠が適用されることがありますが、受取人が他の親族や第三者の場合、相続税が加算される可能性があるため注意が必要です。
また、死亡退職金は相続財産とは異なり、遺産分割の対象にはなりません。つまり、相続人が遺産分割協議を行ったとしても、死亡退職金はその協議の中には含まれず、受取人が直接受け取ることになります。
生前に受けた贈与財産
生前に受けた贈与財産は、みなし相続財産の一つとして重要な位置を占めています。具体的には、被相続人から生前に贈与された財産が、相続税の課税対象となる場合があります。
贈与財産がみなし相続財産として扱われるのは、被相続人の死亡を原因として取得するためです。この場合、贈与が行われた時期や金額によって、課税のルールが異なることがあります。
特に、贈与税の非課税枠を超える金額が贈与された場合、相続税が課税される可能性が高くなります。したがって、贈与を受けた際には、その金額やタイミングをしっかりと把握しておくことが重要です。
また、贈与財産がみなし相続財産として扱われる場合、相続放棄を行ったとしても、その財産を受け取ることができます。しかし、相続放棄をした相続人は、非課税枠を適用できないため、注意が必要です。生前贈与を受けた場合は、相続税の計算においても影響を及ぼすため、事前に専門家に相談することをお勧めします。
その他のみなし相続財産
みなし相続財産には、生命保険金や死亡退職金、生前贈与のほかにもさまざまな種類があります。これらは法律上の相続や遺贈とは異なり、被相続人の死亡を原因として取得されるため、相続税の課税対象となります。
具体的には、被相続人が所有していた不動産や金融資産が、特定の条件を満たす場合にみなし相続財産として扱われることがあります。
例えば、被相続人が生前に契約した投資信託や株式などの金融商品が、死亡時にその評価額が相続人に引き継がれる場合、これもみなし相続財産に該当します。
また、特定の条件下での贈与契約が成立している場合、贈与された財産もみなし相続財産として扱われることがあります。
このように、みなし相続財産は多岐にわたるため、相続税の計算や申告の際には注意が必要です。特に、これらの財産がどのように評価され、課税されるのかを理解しておくことが重要です。
みなし財産の特徴とは

みなし相続財産にはいくつかの特徴があります。これから解説する特徴を理解することで、適切な相続税対策が可能となります。
被相続人の死亡を原因として取得する財産である
みなし相続財産は、被相続人の死亡を原因として取得される財産であるため、その性質上、相続税の課税対象となります。具体的には、相続や遺贈によるものではなく、法律上の相続財産とは異なる扱いを受けます。
例えば、生命保険金や死亡退職金は、被相続人が生前に契約したものであり、死亡時に受取人に支払われるため、相続財産とは区別されます。
このように、みなし相続財産は被相続人の死によって発生するものであり、受取人はその財産を取得する際に相続税の申告を行う必要があります。
相続税の課税対象となるため、受取人はその額面に応じた税金を支払う義務がありますが、一定の条件を満たすことで非課税枠が適用される場合もあります。このため、みなし相続財産を取得する際には、税務上の取り扱いや申告手続きについて十分に理解しておくことが重要です。
法律上は相続や遺贈によるものではない
みなし相続財産は、法律上の相続や遺贈とは異なる形で取得される財産です。通常、相続財産は被相続人の遺志に基づいて分配されるものであり、遺言書や法定相続に従って相続人に引き継がれます。
しかし、みなし相続財産は被相続人の死亡を原因として、特定の条件下で自動的に取得されるため、相続や遺贈の枠組みには含まれません。
具体的には、生命保険金や死亡退職金などが代表的な例です。これらの財産は、被相続人が生前に契約した保険や退職金制度に基づいて支払われるものであり、相続人がその取得を選択することはできません。
また、法律上の相続や遺贈によるものではないため、みなし相続財産は相続分割の対象にもなりません。つまり、相続人間での遺産分割協議において、みなし相続財産は考慮されないのです。
相続税の課税対象となる
みなし相続財産は、被相続人の死亡を原因として取得される財産でありながら、法律上は相続や遺贈によるものではありません。しかし、これらの財産は相続税の課税対象となるため、注意が必要です。具体的には、生命保険金や死亡退職金、生前贈与の一定額などが該当します。
相続税が課税される場合、取得した財産の評価額に基づいて税額が算出されます。特に、生命保険金や死亡退職金は、受取人が誰であるかによって税率が異なるため、受取人の選定や申告方法には慎重を期す必要があります。
また、これらの財産には非課税枠が設けられている場合もありますが、その適用条件を理解しておくことが重要です。
このように、みなし相続財産は相続税の課税対象となるため、相続人はその取り扱いについて十分な知識を持ち、適切な手続きを行うことが求められます。相続税の申告や納付を怠ると、後々トラブルの原因となることもあるため、注意が必要です。
一定の条件下で非課税枠が適用される場合がある
みなし相続財産に関しては、特定の条件を満たすことで非課税枠が適用される場合があります。例えば、生命保険金や死亡退職金などは、受取人が配偶者や子供である場合、一定の金額まで非課税となることがあります。
この非課税枠は、相続税の負担を軽減するための重要な制度であり、特に家族にとっては大きなメリットとなります。
具体的には、生命保険金の場合、受取人が法定相続人であれば、500万円×法定相続人の人数までが非課税となります。
また、死亡退職金についても、同様に非課税枠が設けられており、受取人が法定相続人であれば、一定の金額まで非課税となります。これにより、相続税の負担を軽減し、残された家族が経済的に安定する手助けとなります。
ただし、非課税枠の適用を受けるためには、受取人が法定相続人であることが条件となります。したがって、受取人が配偶者や子供以外の場合、非課税枠は適用されず、相続税が課税されることになります。
みなし相続財産を取得する場合の注意点
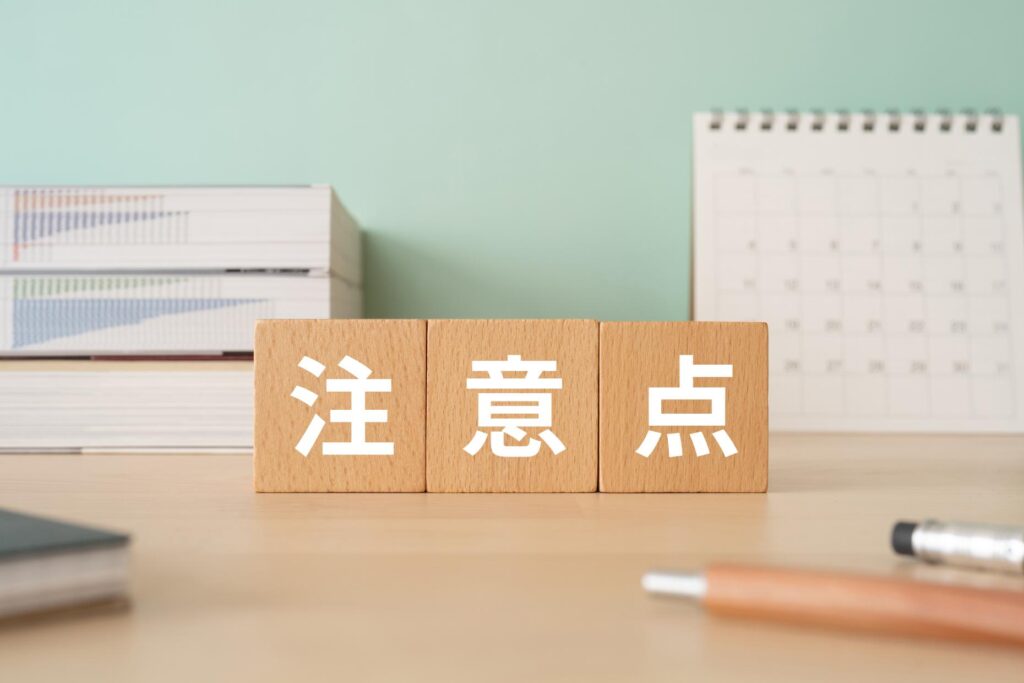
みなし相続財産を取得する際には、いくつかの重要な注意点があります。そのためみなし相続財産を取得する場合は、これから解説する注意点に気をつけて進めていくことが重要です。
みなし相続財産は相続放棄しても受け取れる
みなし相続財産の特徴の一つは、相続放棄を行った場合でも受け取ることができる点です。通常、相続放棄を選択した場合、被相続人の財産全体を放棄することになりますが、みなし相続財産に関してはその限りではありません。
これは、みなし相続財産が法律上の相続や遺贈によるものではなく、被相続人の死亡を原因として取得する財産であるためです。
具体的には、生命保険金や死亡退職金などが該当します。これらの財産は、相続放棄をした相続人であっても、受取人として指定されている場合には、問題なく受け取ることができます。
ただし、みなし相続財産を受け取る場合には、相続税の課税対象となることを忘れてはいけません。受け取った財産に対しては、相続税が課せられる可能性があるため、事前に税務署や専門家に相談し、適切な対策を講じることが求められます。
このように、相続放棄を行った場合でも、みなし相続財産を受け取ることができるため、相続に関する知識を深めておくことが大切です。
みなし相続財産は遺産分割は対象外である
みなし相続財産は、相続財産とは異なり、遺産分割の対象にはなりません。相続財産は被相続人の遺志や法定相続分に基づいて分配されるものであり、遺産分割協議を経て相続人間で分けられます。
一方、みなし相続財産は、被相続人の死亡を原因として直接的に取得する財産であり、相続人がその取得を選択することはできません。
例えば、生命保険金や死亡退職金は、被相続人の死亡時に受取人に直接支払われるため、遺産分割協議の対象外となります。このため、相続人が遺産分割を行ったとしても、みなし相続財産はその分配に影響を与えないのです。
これにより、相続人間での公平性が保たれる一方で、みなし相続財産を受け取る側は、相続税の課税対象となることを理解しておく必要があります。
このように、みなし相続財産は遺産分割の枠組みから外れているため、相続人はその取り扱いについて十分に注意を払うことが求められます。特に、みなし相続財産を受け取る場合には、相続税の申告や非課税枠の適用条件についても確認しておくことが重要です。
相続放棄した相続人は非課税枠を適用できない
みなし相続財産を取得する際、相続放棄を選択した相続人には特に注意が必要です。相続放棄を行うと、その相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになりますが、同時にみなし相続財産に関しても影響が出ます。
具体的には、相続放棄をした相続人は、みなし相続財産に対する非課税枠を適用することができません。
非課税枠とは、一定の条件を満たす場合に相続税が課税されない金額のことを指します。例えば、生命保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられていることがありますが、相続放棄をした場合、その恩恵を受けることができないのです。
これは、相続放棄を行ったことで、法律上その相続人が被相続人の財産に対する権利を放棄したと見なされるためです。
したがって、相続放棄を検討している場合は、みなし相続財産の非課税枠についても十分に理解し、慎重に判断することが重要です。
相続放棄を選択することで、税負担を軽減できる場合もありますが、同時に非課税枠の適用を受けられないリスクもあるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
相続放棄した相続人は非課税枠を適用できない
相続放棄を選択した相続人は、みなし相続財産に対する非課税枠を適用することができません。相続放棄とは、被相続人の遺産を一切受け取らないという法的手続きであり、これにより相続人は相続財産だけでなく、相続債務も引き継がないことになります。
しかし、相続放棄を行った場合、みなし相続財産に関しては特別な扱いがされるため、注意が必要です。具体的には、生命保険金や死亡退職金などのように、被相続人の死亡を原因として取得する財産は、相続放棄をした相続人にとっても受け取ることが可能です。
しかし、相続放棄を行ったことで、これらの財産に対する非課税枠が適用されないため、相続税が発生する可能性があります。これは、相続放棄をした相続人が、相続税の計算においてその財産を考慮しないためです。
したがって、相続放棄を検討している場合は、みなし相続財産の取り扱いや税務上の影響について十分に理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
配偶者・子供・両親以外がみなし相続財産を受け取ると相続税が2割加算される
みなし相続財産を受け取る際には、受取人の関係性によって相続税の課税が異なる点に注意が必要です。
特に、配偶者や子供、両親以外の親族がみなし相続財産を受け取る場合、相続税が通常の税率に加えて2割加算されることになります。この加算は、相続税の負担を大きくする要因となるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
例えば、兄弟や叔父、叔母などの親族が生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、通常の相続税率に加え、20%の加算が適用されます。このため、相続税の計算を行う際には、受取人の関係性を明確にし、適切な税率を適用することが求められます。
また、みなし相続財産の受取人が配偶者や子供、両親でない場合、相続税の負担が増えるだけでなく、相続計画を立てる際にも影響を及ぼす可能性があります。
したがって、相続財産の分配を考える際には、受取人の関係性を考慮し、税負担を軽減する方法を検討することが賢明です。
まとめ
みなし相続財産について理解を深めることは、相続税の適切な対策を講じる上で非常に重要です。みなし相続財産は、法律上の相続や遺贈とは異なる形で取得される財産でありながら、相続税の課税対象となるため、注意が必要です。
生命保険金や死亡退職金、生前贈与の一定額など、具体的な種類を把握し、それぞれの課税ルールを理解することで、無駄な税負担を避けることができます。
また、みなし相続財産を取得する際には、相続放棄の影響や非課税枠の適用条件についても十分に考慮する必要があります。特に、配偶者や子供以外の受取人がいる場合には、相続税が加算されることもあるため、事前に専門家に相談することをお勧めします。
相続に関する知識を深め、適切な手続きを行うことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現することができるでしょう。相続に関する法律や税制は複雑ですが、正しい情報をもとに行動することで、安心して相続を進めることが可能です。



