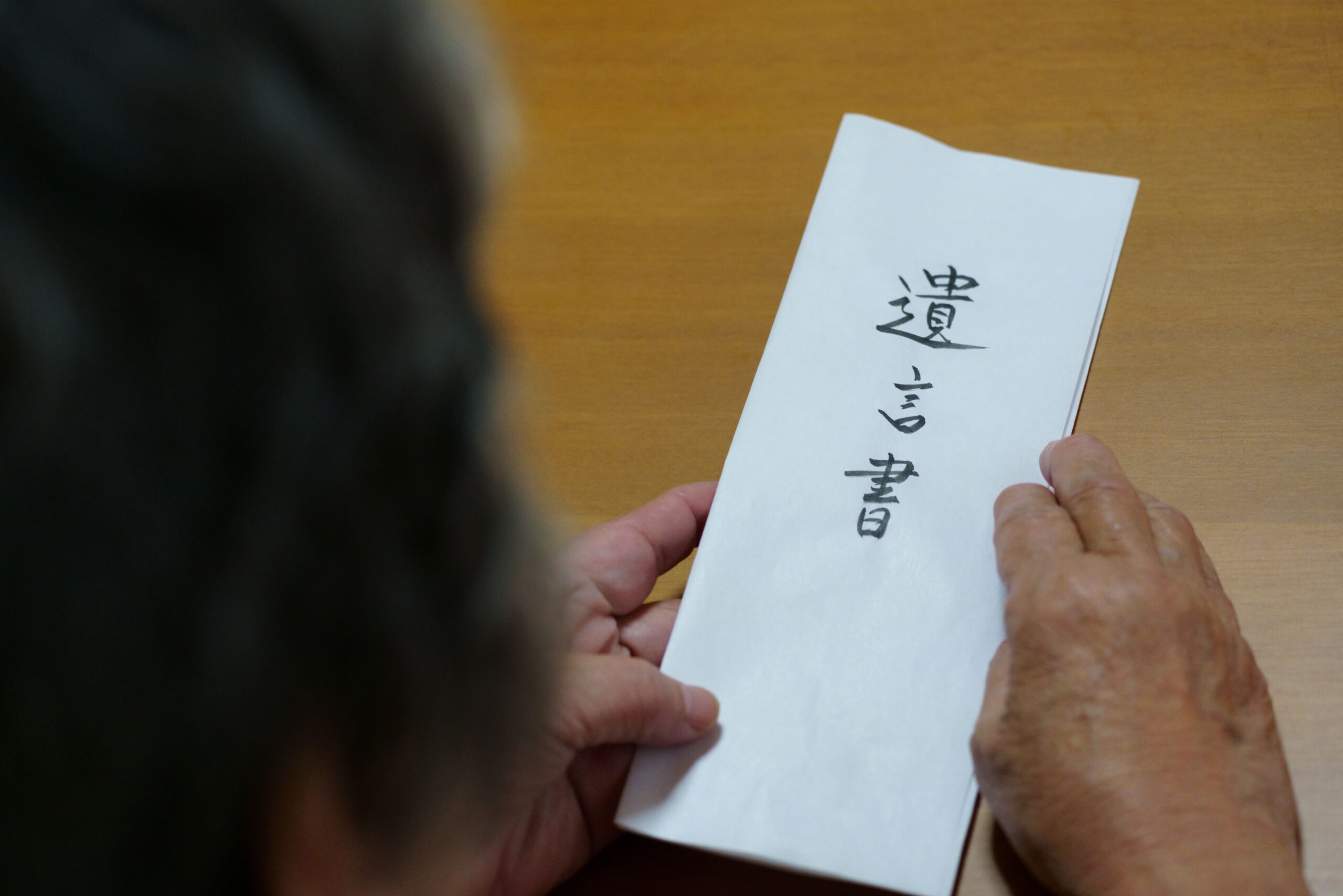認知症の遺言書は有効?遺言能力の判断基準ややるべきことを解説
認知症でも遺言書は有効なのか疑問に思う方は多いでしょう。判断能力が欠けた状態で作成された遺言は無効となるため、作成時点の認知機能を示す証拠を残す準備が欠かせません。
本記事では、遺言能力を判断する医学的・法律的基準と、発症前に取るべき対策、相続人や遺言執行者が注意すべきポイントを詳しく解説します。
認知症でも遺言書は有効なのか
認知症と診断されたからといって直ちに遺言書が無効になるわけではありません。遺言の有効性を左右するのは、遺言書を作成した「その時点」で遺言者が自己の財産内容と相続関係を理解し、誰にどの財産を与えるかという意思を合理的に形成・表現できたかどうか、すなわち遺言能力の有無です。
民法961条は15歳以上であれば遺言できると規定しており、認知症の有無は直接の要件ではありません。実務でも、診療録や心理検査結果で症状の安定が確認され、公正証書遺言作成時に公証人と証人が質問し反応を議事録に残したケースでは、アルツハイマー型認知症の軽中期患者が作成した遺言が有効と判断された例が複数存在します。
一方、判断力が著しく低下していた場合や、遺言内容が生前の言動と大きく矛盾し、作成経緯に不自然な付き添いが認められる場合には無効判決が出ることもあります。
こうしたリスクを下げるには、公正証書方式や法務局保管制度の活用、医師の同席、面談録音を組み合わせ、将来の紛争に備えた証拠を多面的に残すことが重要です。
遺言者の遺言能力を判断する基準とは

遺言者の遺言能力を判断するためには、いくつかの基準があります。これから解説する基準を総合的に判断することで、遺言の有効性が決まります。
認知症の状態・程度
認知症の状態や程度は、遺言能力を判断する上で非常に重要な要素です。認知症は進行性の疾患であり、初期段階では軽度の記憶障害や判断力の低下が見られることがありますが、進行するにつれてこれらの症状は悪化し、最終的には日常生活に支障をきたすことが多くなります。
遺言書を作成する際には、遺言者がその時点でどの程度の認知機能を保持しているかが問われます。具体的には、遺言者が自分の財産や相続人について理解し、適切に意思表示ができるかどうかが判断基準となります。
例えば、遺言者が自分の財産の内容や相続人の名前を正確に把握できている場合、遺言能力があると見なされる可能性が高いです。
一方で、認知症が進行し、判断力が著しく低下している場合、遺言書の有効性が疑問視されることがあります。特に、遺言者が自分の意志を正確に表現できない状態で作成された遺言書は、無効とされるリスクが高まります。
遺言書の内容
遺言書の内容は、遺言者の遺言能力を判断する重要な要素の一つです。具体的には、遺言書に記載された内容が遺言者の意思を反映しているかどうか、またその内容が合理的であるかがポイントとなります。
認知症の進行度によっては、遺言者が自分の財産や相続人について正確に理解し、適切な判断を下すことが難しくなるため、内容の整合性が問われることがあります。
例えば、遺言書に記載された相続分が不公平であったり、特定の相続人に対して不当な扱いがされている場合、遺言者の判断能力が疑問視されることがあります。
また、遺言書の内容が遺言者の生前の言動や意向と矛盾している場合も、遺言能力の判断に影響を与える可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際には、遺言者が自分の意思を明確に表現できる状態であることが重要です。遺言書の内容が遺言者の真意を反映しているかどうかを確認するためには、専門家の助言を受けることも有効です。
遺言書作成時・作成前後の言動
遺言書の有効性を判断する際、遺言者の作成時やその前後の言動は非常に重要な要素となります。特に認知症の進行度によっては、遺言者が自らの意思を明確に表現できているかどうかが、遺言の有効性に大きく影響します。
まず、遺言書を作成する際の言動が重要です。遺言者が自分の財産や相続人について具体的に理解し、意図を持って遺言書を作成しているかどうかがポイントです。
例えば、遺言書の内容について質問した際に、遺言者がしっかりと答えられるか、またその内容に対して納得している様子が見られるかどうかが、判断材料となります。
次に、遺言書作成前後の言動も考慮されます。遺言者が遺言書を作成する前に、相続についての話をしていたり、特定の財産についての意向を示していた場合、その言動は遺言の意図を裏付ける証拠となります。
また、遺言書作成後に遺言者がその内容について再確認したり、他者に説明する姿勢が見られる場合も、遺言能力の証明に寄与します。
遺言書作成の経緯や動機
遺言書の有効性を判断する際には、作成の経緯や動機が重要な要素となります。特に認知症の方が遺言書を作成する場合、その背景にある意図や理由が明確であることが、遺言能力の証明に繋がります。
例えば、遺言者が特定の相続人に対して特別な配慮を示すために遺言書を作成した場合、その動機が理解されることで、遺言の内容がより信頼性を持つことになります。
また、遺言書作成の経緯についても注意が必要です。遺言者がどのような状況で遺言書を作成したのか、例えば、家族との話し合いや専門家の助言を受けた上での決定であったかどうかが、遺言の有効性を左右します。
さらに、遺言書の作成に至るまでの過程や、遺言者が抱えていた思いや希望を記録しておくことも大切です。
これにより、後々遺言能力が争われた際に、遺言者の意図を明確に示す材料となります。したがって、遺言書を作成する際には、その経緯や動機をしっかりと整理し、必要に応じて証拠を残しておくことが推奨されます。
認知症になる前に遺言者がやるべきこととは

認知症の進行を防ぐためには、遺言者が元気なうちにしっかりと遺言書を作成することが重要です。これから解説する対策を講じることで、安心して遺言を残すことができます。
遺言能力があるうちに遺言書を作成する
認知症の進行に伴い、判断能力が低下することは避けられません。そのため、遺言書を作成する際には、遺言能力があるうちに行動を起こすことが重要です。
遺言能力とは、自分の財産や相続人について理解し、適切に意思表示を行うことができる能力を指します。この能力が欠けてしまうと、作成した遺言書が無効とされる可能性が高まります。
遺言書を作成する際には、まず自分の意志を明確にし、どのように財産を分配したいのかを考えることが必要です。具体的には、相続人の名前やそれぞれに与える財産の内容を詳細に記載することが求められます。
また、遺言書を作成する際には、信頼できる人に相談し、必要に応じて専門家の助言を受けることも大切です。さらに、遺言書を作成するタイミングも重要です。認知症の初期段階であれば、まだ判断能力が残っている可能性が高いです。
この時期に遺言書を作成することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。遺言書を作成することは、自分の意志を尊重し、家族や親しい人々に対する配慮でもあります。
公正証書遺言を作成する
認知症のリスクがある場合、遺言書を作成する際には公正証書遺言を選ぶことが非常に重要です。公正証書遺言とは、公証人が立ち会いのもとで作成される遺言書であり、法律的な効力が高いとされています。この形式の遺言書は、遺言者の意思を明確に示すことができるため、後々のトラブルを避けるためにも有効です。
公正証書遺言を作成するためには、まず公証役場に予約を取り、必要な書類を準備する必要があります。具体的には、遺言者の本人確認書類や、遺言の内容を証明するための資料が求められます。
また、遺言の内容については、事前にしっかりと考えておくことが大切です。公証人は、遺言者の意思を確認するために、遺言の内容について質問を行うことがありますので、スムーズに進めるためにも準備が欠かせません。
さらに、公正証書遺言は、遺言者が認知症の症状を抱えている場合でも、その状態に応じた判断能力が求められます。公証人は、遺言者の精神状態を確認し、遺言能力があると判断した場合にのみ、遺言書を作成することができます。
遺言執行者を指定する
遺言書を作成する際には、遺言執行者を指定することが重要です。遺言執行者とは、遺言の内容を実行する責任を持つ人物であり、相続手続きや遺産分割を円滑に進める役割を果たします。
特に認知症のリスクがある場合、遺言執行者を事前に指定しておくことで、遺言の実行がスムーズに行われる可能性が高まります。遺言執行者には、信頼できる親族や友人、あるいは専門家(弁護士や司法書士など)を選ぶことができます。
選任された遺言執行者は、遺言の内容に従って遺産を分配し、相続人との調整を行います。遺言執行者を指定することで、遺言の内容が正確に実行されることが期待でき、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
また、遺言執行者を指定する際には、その人物に対して事前に相談し、承諾を得ることが大切です。遺言執行者がその役割を果たすことに同意しているかどうかを確認することで、後々のトラブルを避けることができます。
遺言能力が争われたときの証拠を残しておく
認知症の進行に伴い、遺言能力が争われるケースは少なくありません。そのため、遺言書を作成する際には、遺言者の判断能力を証明するための証拠を残しておくことが重要です。具体的には、遺言書作成時の状況や、遺言者の言動を記録しておくことが求められます。
まず、遺言書を作成する際には、信頼できる第三者に立ち会ってもらうことが有効です。立会人がいることで、遺言者が自らの意思で遺言書を作成したことを証明する材料となります。
また、遺言書作成時の映像や音声を記録することも、後々の争いを避けるための強力な証拠となります。さらに、遺言書の内容が遺言者の意向を反映していることを示すために、遺言者がその内容について十分に理解していたことを示す証拠も必要です。
例えば、遺言書の内容についての説明を受けた際のメモや、専門家との相談記録などが考えられます。このように、遺言能力が争われた場合に備えて、事前に証拠を整えておくことは、遺言者自身の意向を尊重し、相続人間のトラブルを未然に防ぐために非常に重要です。
認知症になったら診断書を取る
認知症と診断された場合、遺言書の有効性を確保するために診断書を取得することが重要です。診断書は、医師が認知症の状態や程度を評価した公式な文書であり、遺言能力の判断において重要な証拠となります。遺言書が作成された時点での判断能力を証明するためには、診断書が必要不可欠です。
診断書を取得する際は、専門の医療機関での診断を受けることが望ましいです。認知症の症状は個人によって異なるため、医師による適切な評価が求められます。
また、診断書には、認知症の種類や進行度、日常生活における影響などが記載されることが一般的です。これにより、遺言書作成時の判断能力を客観的に示すことができます。
さらに、診断書は遺言書の作成後も保管しておくことが重要です。万が一、遺言能力が争われる事態が発生した場合、診断書があれば、遺言者がその時点でどのような状態であったかを証明する材料となります。
相続人が認知症の場合の注意点

相続人が認知症を患っている場合、いくつかの重要な注意点があります。これから解説する点を理解し、適切な対策を講じることが重要です。
遺産分割協議はできない
認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議とは、相続人が集まり、故人の遺産をどのように分けるかを話し合うプロセスですが、認知症の相続人はその判断能力が欠けているため、協議に参加することができないのです。
具体的には、認知症の相続人がいる場合、その人の意見や意思を尊重することが難しくなります。したがって、遺産分割協議を進めるためには、認知症の相続人が法的に有効な判断を下せる状態であることが求められます。
もし、その相続人が判断能力を欠いている場合、協議は成立せず、遺産の分配が滞ることになります。このような状況を避けるためには、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書があれば、故人の意思に基づいて遺産を分配することができ、認知症の相続人がいる場合でもスムーズに手続きを進めることが可能になります。したがって、認知症のリスクがある場合は、早めに遺言書を作成し、遺産分割の方針を明確にしておくことが推奨されます。
認知症の相続人は相続放棄できない
認知症を患っている相続人がいる場合、その相続人が相続放棄を行うことはできません。相続放棄とは、相続人が自らの権利を放棄することであり、通常は相続人が自分の意思で行う必要があります。
しかし、認知症の状態にある相続人は、判断能力が欠けているため、自らの意思で相続放棄をすることができないのです。このため、認知症の相続人がいる場合、相続放棄を希望する他の相続人は、法的手続きを通じてその相続人の権利を放棄させることが難しくなります。
具体的には、認知症の相続人が相続放棄を行うためには、家庭裁判所に対して成年後見人の選任を申し立て、その後に成年後見人が相続放棄を行う必要があります。この手続きは時間がかかる上、費用も発生するため、事前に認知症のリスクを考慮した相続対策が重要です。
また、認知症の相続人が相続放棄を行えない場合、相続財産に対する責任も引き継がれることになります。
つまり、相続人が負債を抱えている場合、その負債も相続されることになるため、注意が必要です。相続人が認知症である場合、相続に関する法律や手続きについて専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
認知症の人の代わりに何かを代筆する行為は無効になる
認知症の方が遺言書を作成する際、本人の意思を尊重することが重要です。しかし、認知症の進行により本人が自らの意思を表現できない場合、家族や親しい人が代わりに遺言書を作成することを考えるかもしれません。しかし、このような代筆行為は法律的に無効とされることが多いのです。
遺言書は、遺言者の明確な意思を示すものでなければなりません。認知症の方が自らの意思を表現できない場合、その代わりに他者が書いた内容は、遺言者の真の意志を反映しているとは言えません。したがって、代筆された遺言書は、遺言能力が欠如していると見なされ、無効とされるリスクが高いのです。
また、代筆行為が行われた場合、遺言書の内容が遺言者の意向に沿ったものであるかどうかを証明することが難しくなります。
これにより、相続人間でのトラブルや法的な争いが生じる可能性もあります。したがって、認知症の方が遺言を残す必要がある場合は、本人が自らの意思を示せるうちに、適切な方法で遺言書を作成することが重要です。
まとめ
認知症の影響を受けた場合でも、遺言書が有効となるためには、遺言者の遺言能力が重要な要素となります。遺言能力は、認知症の状態や程度、遺言書の内容、作成時の言動、さらには遺言書作成の経緯や動機など、さまざまな要因によって判断されます。これらの基準を理解し、適切な対策を講じることが、遺言書の有効性を確保するためには欠かせません。
特に、認知症になる前に遺言書を作成し、公正証書遺言を選択することは、遺言能力を証明するための強力な手段となります。
また、遺言執行者を指定し、必要な証拠を残しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。認知症の診断を受けた際には、速やかに診断書を取得することも重要です。
相続人が認知症の場合には、遺産分割協議ができないことや、相続放棄ができないこと、代筆行為が無効になることなど、特有の注意点があります。これらの知識を持つことで、相続に関する問題を円滑に進めることができるでしょう。