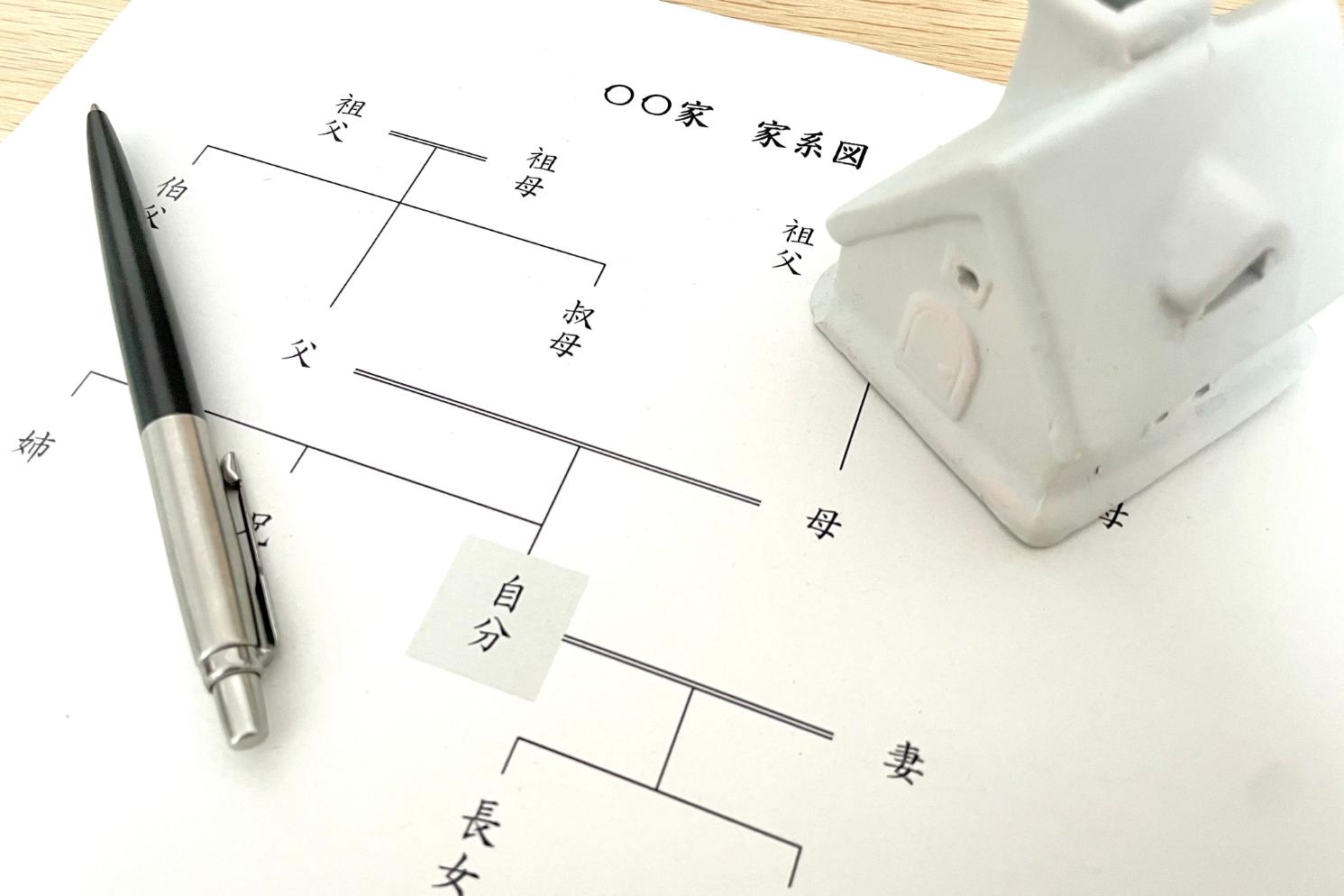二次相続とは?注意点や対策方法、相続税の節税対策について解説!
二次相続とは一次相続で配偶者が財産を取得した後、その配偶者が死亡した際に発生する相続で、基礎控除縮小や配偶者控除不適用により税負担が増える傾向があります。
本記事では一次相続との違い、注意点、生前贈与や資産分散、保険活用など節税対策を時系列で整理し、将来の税負担を抑えるポイントを解説します。早めの対策で次世代への負担を軽減し、円滑な資産承継を目指しましょう。
二次相続とは

二次相続とは、一次相続で配偶者が受け継いだ財産につき、その配偶者が死亡した際に子や孫などの後順位相続人が改めて承継する二度目の相続を意味します。
一次相続では「配偶者の税額軽減」により1億6000万円または法定相続分まで非課税となり、相続人の人数が多いため基礎控除額も拡大し、税負担は抑えられるのが一般的です。
しかし、配偶者死亡後の二次相続では相続人が子だけになるケースが多く、基礎控除「3000万円+600万円×人数」が縮小します。さらに、配偶者控除は適用されず、一次相続で集約された不動産や金融資産が全額課税ベースに計上されるため、課税ラインを大きく超過しやすい構造です。
国税庁統計でも二次相続の課税割合は一次相続の約1・5倍に増加しています。短期間に二度目の納税資金を確保する必要が生じ、延納や物納に追い込まれる例も散見されます。
生前贈与、小規模宅地等特例、配偶者居住権、生命保険非課税枠などを組み合わせた総合的な資産移転計画を一次相続時点から専門家と策定し、海外資産や暗号資産の所在も共有して申告漏れを防ぐ備えが欠かせません。
二次相続の注意点とは

二次相続においては、いくつかの重要な注意点があります。これから解説する注意点をしっかり踏まえ、二次相続を進めていきましょう。
相続税の基礎控除額が減る
相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。一次相続が配偶者と子2人なら控除は4200万円ですが、配偶者死亡後の二次相続では子2人だけになり3600万円へ600万円縮小します。
また、控除が減るだけでなく、一次相続で配偶者に集中させた財産全体が子へ移るため評価額は大きく膨らみ、課税ラインを容易に突破します。地価上昇や株価回復の追い風があると控除縮小の影響はさらに拡大し、預金だけで納税額を捻出できず不動産売却を余儀なくされる例も多いです。
対策として、一次相続時に子へ現物分割を実施して課税ベースを縮小する、教育資金や結婚子育て資金贈与の非課税枠を活用して評価額を圧縮する、孫養子縁組で相続人を増やして基礎控除をかさ上げするなどの方策が考えられます。
さらに、基礎控除縮小に気付かず申告漏れが生じると、追徴課税や重加算税の対象となるため特に注意が必要です。
基礎控除を過信して無申告となると、無申告加算税や延滞税に加え重加算税が課されるリスクもあるため、早い段階で税理士にシミュレーションを依頼し、控除縮小の影響を数値で把握することが望まれます。
二次相続では配偶者控除が使えない
一次相続では「配偶者の税額軽減」により、配偶者が取得する財産は法定相続分または1億6000万円のいずれか大きい額まで相続税が非課税になります。
ところが、配偶者自身が死亡して発生する二次相続では、この特例は当然適用されず、配偶者が保有していた不動産や預貯金、株式が全額課税ベースに算入されます。その結果、累進課税の高率帯に一気に跳ね上がり、予想を超える税額請求を受けることも珍しくありません。
配偶者に資産を集中させすぎると二次相続で課税負担が爆発するため、一次相続時点で子へ一定割合を現物分割する、配偶者には居住用宅地のみを残して小規模宅地等特例(80%評価減)を確実に適用する、養子縁組で人数を増やして基礎控除を拡大するなど、二段階相続を前提とした資産配分が重要です。
さらに、生命保険を子受取に変更して現金納税原資を確保し、延納・物納の利用可能性と条件を試算しておくことで、課税ショックへの備えが万全になります。
配偶者が高齢の場合には、介護医療費を考慮した資金留保と節税策のバランスも検討し、家族信託や任意後見契約を活用して管理コストと移転手続きを整理しておくと、納税後の資産運用もスムーズです。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が小さくなる
二次相続においては、死亡保険金や死亡退職金に対する非課税枠が一次相続に比べて小さくなるため、注意が必要です。一次相続では、配偶者や子どもが受け取る死亡保険金に対して、一定の非課税枠が設けられていますが、二次相続ではこの枠が縮小されることが一般的です。
具体的には、死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数となりますが、相続人が増えることで相続税の負担が大きくなる可能性があります。
また、死亡退職金についても同様のことが言えます。一次相続の際には、受取人が配偶者や子どもであれば、非課税枠が適用されますが、二次相続ではその適用が制限されることが多く、結果として相続税の負担が増加することになります。
このような非課税枠の縮小は、相続税の負担を増加させる要因となるため、早めに対策を講じることが求められます。具体的には、生命保険の受取人を見直したり、死亡退職金の受取方法を工夫することで、税負担を軽減することが可能です。
二次相続の対策方法とは

二次相続においては、税負担を軽減するための対策が重要です。これから解説する対策方法をしっかり行うことで、二次相続をスムーズに進めることができます。
生前贈与を行う
生前贈与は、二次相続における税負担を軽減するための有効な手段の一つです。一次相続で配偶者が財産を取得した後、その配偶者が亡くなった際に発生する二次相続では、相続税の基礎控除が縮小され、配偶者控除が適用されないため、税負担が増加する傾向があります。
このような状況を回避するためには、早めに生前贈与を行うことが重要です。生前贈与を行うことで、相続財産を減少させることができ、結果として相続税の負担を軽減することが可能です。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内で贈与を行うことで、贈与税が発生しないため、計画的に贈与を行うことが推奨されます。また、贈与を受けた財産は、受贈者の名義となるため、相続時にその財産が相続財産から除外されることになります。
さらに、特定の条件を満たす場合には、教育資金や結婚資金の贈与に対しても非課税枠が設けられています。これらの制度を活用することで、より多くの資産を次世代にスムーズに移転することができ、二次相続時の税負担を軽減することができます。
配偶者の資産を増やさない
二次相続において、配偶者の資産を増やさないことは非常に重要な対策の一つです。一次相続で配偶者が財産を取得した後、配偶者が亡くなると、その財産が二次相続の対象となります。この際、相続税の基礎控除額が減少し、配偶者控除も適用されないため、税負担が大きくなる可能性があります。
そのため、配偶者が相続する財産をできるだけ減らす工夫が求められます。具体的には、配偶者名義の資産を増やさないようにすることが効果的です。
例えば、配偶者が所有する不動産や金融資産を子ども名義に移すことで、配偶者の資産を減少させることができます。このような資産の移転は、早めに行うことで相続税の負担を軽減することが可能です。
また、配偶者が受け取る遺産の内容を見直し、必要のない資産を整理することも重要です。例えば、使用していない不動産や高額な金融商品を売却し、その資金を生活資金や必要な資産に充てることで、相続時の資産を減らすことができます。
このように、配偶者の資産を増やさないための対策を講じることは、二次相続における税負担を軽減するための有効な手段です。
生命保険を活用する
二次相続において、生命保険は非常に有効な対策手段となります。生命保険の受取人を配偶者や子どもに設定することで、相続財産とは別に保険金を受け取ることができ、相続税の負担を軽減することが可能です。
特に、死亡保険金には一定の非課税枠が設けられており、この枠を利用することで、相続税の課税対象となる財産を減少させることができます。
また、生命保険は資産の流動性を高める役割も果たします。相続が発生した際、現金が必要となる場面が多々ありますが、保険金は迅速に受け取ることができるため、相続手続きに伴う費用や税金の支払いに充てることができます。
さらに、生命保険を利用する際には、保険の種類や契約内容を慎重に選ぶことが重要です。特に、終身保険や定期保険など、さまざまな選択肢があるため、ライフプランや相続計画に応じた最適な保険を選ぶことが求められます。
子どもに実家を相続させる
子どもに実家を相続させることは、二次相続における重要な対策の一つです。一次相続で配偶者が財産を取得した後、配偶者が亡くなった際に、実家が子どもに相続されることで、相続税の負担を軽減することが可能です。
特に、実家が居住用不動産である場合、小規模宅地等の特例を利用することで、評価額を大幅に下げることができ、相続税の負担を軽減する効果があります。
また、子どもに実家を相続させる際には、事前に相続の意向をしっかりと伝えておくことが重要です。相続に関する話し合いを行うことで、将来的なトラブルを避けることができます。さらに、実家を相続させることで、子どもが住み続けることができ、家族の絆を深めることにもつながります。
ただし、実家を相続させる際には、相続税の計算や不動産の評価についても考慮する必要があります。特に、相続税の基礎控除や配偶者控除が適用されない二次相続では、事前にしっかりとした対策を講じることが求められます。
子どもに実家を相続させることは、将来の税負担を軽減し、円滑な資産承継を実現するための有効な手段と言えるでしょう。
相続をする場合の財産の種類を変更する
二次相続においては、相続財産の種類を見直すことが重要な対策の一つです。相続財産には不動産、現金、株式などさまざまな種類がありますが、それぞれの財産には異なる評価額や税負担がかかります。特に不動産は評価額が高くなる傾向があり、相続税の負担を増加させる要因となります。
そのため、相続を考える際には、現金や金融資産にシフトすることを検討するのが効果的です。現金や預貯金は相続税の評価額が比較的低く、また流動性が高いため、相続後の資産管理が容易になります。
さらに、株式などの金融資産も、適切なタイミングで売却することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
また、相続財産の種類を変更する際には、資産の分散も考慮する必要があります。特定の財産に偏ることなく、複数の資産を持つことで、相続税の負担を分散させることができます。
このように、相続をする場合の財産の種類を変更することは、二次相続における税負担を抑えるための有効な手段です。
相続税に対してやるべき節税対策とは
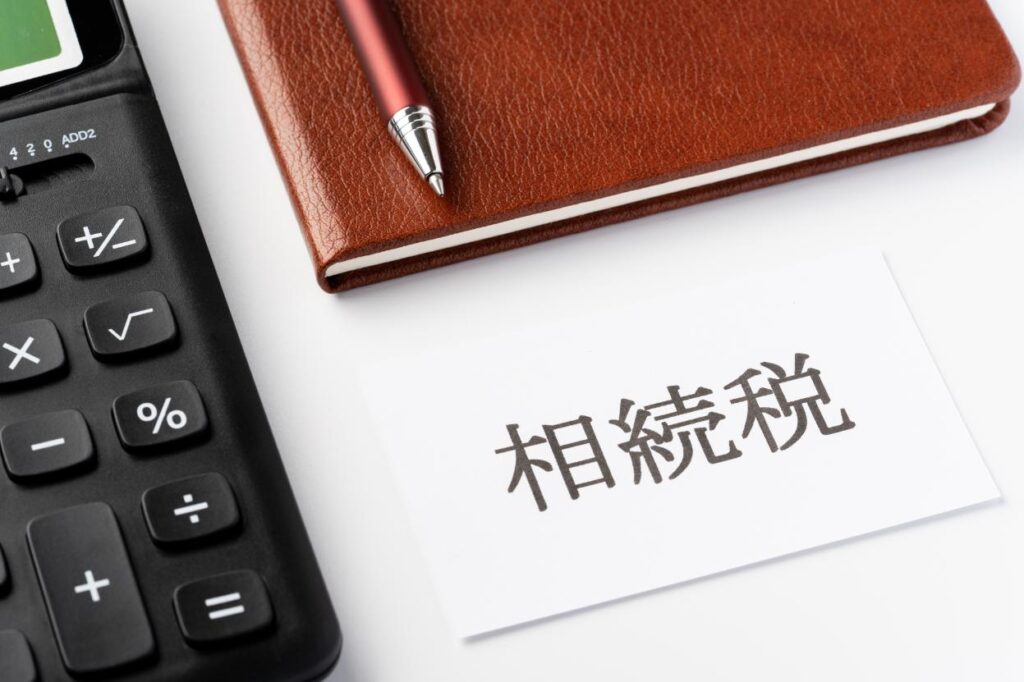
相続税の負担を軽減するためには、いくつかの効果的な節税対策があります。これから解説する対策を検討し、早めに準備を進めることが大切です。
小規模宅地等の特例を利用し、不動産評価額を下げる
相続税の負担を軽減するための有効な手段の一つが、小規模宅地等の特例の活用です。この特例は、被相続人が居住していた宅地や事業用の宅地について、一定の条件を満たす場合に評価額を大幅に減額できる制度です。具体的には、居住用の宅地については最大で80%の減額が可能となります。
この特例を利用するためには、いくつかの要件があります。まず、被相続人がその宅地に居住していたことが必要です。また、相続人がその宅地に引き続き居住することも求められます。さらに、相続開始時点での宅地の面積が240㎡までであることが条件です。
これにより、相続税の評価額が大幅に下がり、結果として税負担を軽減することができます。特例を適用する際には、申告手続きが必要ですので、事前に必要な書類を整えておくことが重要です。
また、特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限内に手続きを行う必要があるため、早めの準備が求められます。小規模宅地等の特例を上手に活用することで、次世代への負担を軽減し、円滑な資産承継を実現することができるでしょう。
死亡退職金の非課税枠を活用する
二次相続において、死亡退職金は重要な資産の一部として考慮されます。この死亡退職金には、一定の非課税枠が設けられており、適切に活用することで相続税の負担を軽減することが可能です。
具体的には、死亡退職金の非課税枠は、受取人が受け取る金額のうち、500万円にその人の勤続年数を掛けた額が非課税となります。例えば、勤続年数が20年であれば、500万円×20年=1億円までが非課税となります。
この非課税枠を最大限に活用するためには、受取人を適切に設定することが重要です。通常、配偶者や子どもが受取人となることが多いですが、受取人の選定によっては、相続税の負担を大きく変えることができます。
また、死亡退職金は、相続財産とは別に扱われるため、相続税の計算においても有利に働くことがあります。さらに、死亡退職金を受け取る際には、受取人がその金額をどのように使うかも考慮する必要があります。
例えば、受け取った金額を生前贈与に充てることで、次世代への資産移転をスムーズに行うことができ、将来的な相続税の負担を軽減することが期待できます。
親子で同居を始める
親子で同居を始めることは、二次相続における相続税対策として非常に有効な手段の一つです。
特に、同居することで生活費や住宅費を共有できるため、経済的な負担を軽減することができます。また、親が亡くなった際に、相続税の負担を軽減するための特例を利用することも可能です。
同居をすることで、親の資産を守るだけでなく、子どもが相続する際の評価額を下げる効果も期待できます。例えば、小規模宅地等の特例を利用することで、居住用の不動産の評価額を大幅に減少させることができ、結果として相続税の負担を軽減することができます。
さらに、親子で同居することで、日常的に親の健康状態を把握しやすくなり、介護やサポートが必要な場合にも迅速に対応できるメリットがあります。これにより、親の生活の質を向上させるだけでなく、相続に関するトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
墓地・仏具を生前にそろえる
相続において、墓地や仏具の準備は重要な要素の一つです。生前にこれらを整えておくことで、相続時の負担を軽減し、遺族がスムーズに手続きを進めることができます。
特に、墓地や仏具は感情的な側面も強く、遺族が故人を偲ぶための大切な場所や物となります。そのため、事前に計画を立てておくことが望ましいです。
生前に墓地を購入することで、相続時に発生する評価額を抑えることができる場合があります。また、仏具についても、必要なものを選んでおくことで、遺族が急いで購入する必要がなくなり、精神的な負担を軽減できます。
さらに、これらの準備を通じて、家族間でのコミュニケーションが深まり、相続に関する意識を高めることにもつながります。
また、墓地や仏具の購入に関しては、地域によって価格や選択肢が異なるため、早めに情報収集を行い、適切な選択をすることが重要です。生前にしっかりと準備をしておくことで、相続時のトラブルを避け、円滑な資産承継を実現することができるでしょう。
相続時精算課税制度を利用する
相続時精算課税制度は、相続税の負担を軽減するための有効な手段の一つです。この制度を利用することで、贈与を受けた財産に対して相続税を事前に計算し、相続時にその分を精算することが可能になります。
具体的には、贈与を受けた際に一定の非課税枠が設けられており、その範囲内であれば贈与税がかからないため、早めに資産を移転することができます。
この制度の大きなメリットは、相続時に発生する税負担を事前に軽減できる点です。特に、相続財産が多い場合や、将来的に相続税が高額になる可能性がある場合には、早期に贈与を行うことで、相続時の税負担を大幅に減少させることができます。
また、相続時精算課税制度を利用することで、贈与を受けた側も早い段階から資産を活用できるため、生活の質を向上させることにもつながります。
ただし、この制度には注意点も存在します。例えば、相続時精算課税制度を選択すると、以後の贈与についてはこの制度が適用されるため、他の贈与税の特例を利用できなくなることがあります。
まとめ
二次相続は、一次相続で配偶者が財産を取得した後、その配偶者が亡くなることで発生する相続です。このプロセスにおいては、相続税の基礎控除額が減少し、配偶者控除が適用されないため、税負担が増加する傾向があります。
本記事では、二次相続の注意点や対策方法について詳しく解説しました。生前贈与や資産分散、生命保険の活用など、さまざまな節税対策を検討することで、将来の税負担を軽減し、円滑な資産承継を実現することができます。
特に、相続税に対する具体的な節税対策を講じることで、家族の財産を守ることができるでしょう。相続は一度きりの大切なプロセスですので、専門家のアドバイスを受けながら、計画的に進めることをお勧めします。